

Same day
Procurement
Diagnostics
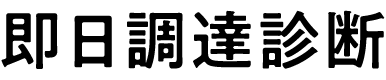
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

ファクタリングを利用する際、利用するサービスによっては「債権譲渡登記」が必要となることがあります。
しかし、「債権譲渡登記ってそもそも何?」「本当に必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
そこで今回は、債権譲渡登記の必要性や登記を行うメリット・デメリットについてご紹介します。
また、債権譲渡登記を行う際の手続きやファクタリング会社を選ぶ際のポイント、登記に関するQ&Aについてもまとめているので、ぜひご参考にしてください。
【注目】資金調達を検討中の事業主様へ
直近の支払いが迫っているなどの理由で資金調達を急ぎたい場合は、売掛金を売却して早期に現金化ができる「ファクタリング」がおすすめです。
ファクタリングを利用すれば最短即日での現金化も叶うため、予期せぬ支払いが発生した場合にもスピーディーに対応できます。
当機構のファクタリングサービスは、審査まで最短30分、入金まで最短3時間で行えます。
また、審査完了まで最短10分、入金まで最短40分で行えるオンライン完結型ファクタリング「FACTOR⁺U(ファクトル)」も提供しているため、急ぎで審査を受けたい方は当機構にお任せください。

債権譲渡登記は、債権を譲渡する際、第三者や取引先(債務者)に対して権利関係を明確にするための制度です。
債権の譲渡自体は当事者間の合意で成立しますが、第三者や債務者にその権利を確実に主張する方法の一つとして、法務局で行う債権譲渡登記があります。
債権譲渡登記では、譲渡人・譲受人の情報や譲渡の対象となる債権、登記の年月日などが記録され、債権の権利関係の優先順位を明確にすることができます。
以下では、債権譲渡登記が必要な理由をご紹介します。
債権の二重譲渡によるトラブルは、債権譲渡登記を行うことで防ぐことが可能です。
二重譲渡とは、同じ債権が複数の相手に譲渡されることを指します。
二重譲渡が行われた場合、対象の債権の権利関係が不明確になるおそれがありますが、債権譲渡登記を行うことで、譲渡の事実が法務局に公示され、どの譲受人(例えばファクタリング会社)が先に権利を取得したかが明確になります。
企業間取引では債権譲渡が頻繁に行われるため、登記による公示は安全な取引の基盤となります。
二重譲渡については下記のコラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは2社目の申し込みも大丈夫?相見積り・掛け持ち・二重譲渡について
債権譲渡登記を行うことで、債権の譲渡事実が法務局に記録され、第三者に対しても公示されます。
これにより、債権譲渡が確かに行われたことを客観的な証拠として残すことが可能です。
また、登記を行うことは「第三者対抗要件」を満たす手段の一つでもあります。
債権譲渡は、債務者やほかの利害関係人など第三者に対しても効力を主張するため、この対抗要件を備えておくことが求められます。
契約書だけでは、譲渡の成立や譲受人の権利を第三者に証明する際に不十分な場合がありますが、登記があれば登記簿に記録された情報が正式な公的記録となるため、裁判や交渉の場でも強力な法的根拠となります。
万が一トラブルが発生した場合は、債権譲渡の事実や優先権の確認が重要となるため、登記によって権利関係を明確に残しておくことが、安全な取引のための重要な手段となります。
第三者対抗要件については下記のコラムで詳しく解説しています。
【ファクタリング】対抗要件とは?債権譲渡に重要な要素を知ろう

ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売却することで、早期に現金化できる金融サービスです。
ファクタリングを利用する際、債権譲渡登記が必要かどうかは、契約の種類や利用するサービスによって異なります。
債権譲渡登記が必要になるケースは、主に2者間ファクタリングを利用するときです。
2者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2者で契約を締結するファクタリングのことです。
2者間ファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛金の存在を直接売掛先に確認することはできません。
そのため、同じ売掛金がほかのファクタリング会社に重複して売却されるリスクがあります。
こうしたリスクを防ぐため、2者間ファクタリングを利用する際には、ファクタリング会社から債権譲渡登記を求められることがあります。
なお、2者間ファクタリングでもファクタリング会社によっては債権譲渡登記を必要としない場合もあります。
2者間ファクタリングについては下記のコラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
一方で、利用者・売掛先・ファクタリング会社の3者で契約を締結する3者間ファクタリングでは、ファクタリングの利用にあたり事前に売掛先からの承諾が必要です。
売掛先の承諾があれば登記を行わなくても売掛金売却の事実を債務者に示すことができますが、第三者に対して効力を持たせるためには確定日付が必要になります。
3者間ファクタリングについては下記のコラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
ファクタリングについては下記のコラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】

ここでは、債権譲渡登記を必須としているファクタリング会社を利用するメリットとデメリットをご紹介します。
債権譲渡登記を必須としているファクタリング会社を利用することで、利用者は以下のようなメリットを受けられます。
債権譲渡登記を行うメリットの一つに、低い手数料でファクタリングを利用できる可能性がある点が挙げられます。
とくに2者間ファクタリングの場合、債権譲渡登記を行うことで売掛金の権利関係や優先順位が法的に明確になることから、ファクタリング会社によっては通常より低い手数料での取引が認められることがあります。
債権譲渡登記を行うメリットに、ファクタリング会社による審査の通過率が高まる可能性がある点も挙げられます。
登記によって売掛金の存在や権利関係が公的に証明されるため、売却対象の売掛金が確実に存在し、優先権が明確であることをファクタリング会社が判断しやすくなります。
その結果、ファクタリング会社の未回収リスクが下がり、審査や条件が有利に進むことが期待できます。
一方で、債権譲渡登記を必須としているファクタリング会社を利用するデメリットは以下の通りです。
債権譲渡登記を行うデメリットに、登記費用が発生する点が挙げられます。
債権譲渡登記は法務局での手続きが必要で、自分で申請することも可能ですが、申請書類の作成や添付書類の準備など、手続きは複雑でミスがあると受理されない場合があります。
そのため、司法書士などの専門家に依頼するケースも少なくありません。
ただし、専門家に依頼すると費用が発生するため、売掛金の額が小さい場合やファクタリングで得られる現金が少ない場合は、手数料や依頼料で手元に残る金額がさらに少なくなってしまう可能性があります。
また、詳しくは後述しますが、上記のほか登録免許税も発生するので、その点は留意しておきましょう。
債権譲渡登記は法人や一部の団体が対象となる制度であり、個人事業主は原則として利用できません。
そのため、個人事業主は債権譲渡登記を条件としているファクタリングサービスを利用できない可能性が高いです。
ただし、債権譲渡登記を不要としているファクタリング会社であれば、個人事業主でも利用可能です。
個人事業主向けのファクタリング会社については下記のコラムで詳しく解説しています。
【2025年最新】個人事業主向けおすすめファクタリング会社15選!少額や即日対応も紹介!
債権譲渡登記を行うデメリットの一つに、売掛先にファクタリングの利用を知られる可能性がある点が挙げられます。
2者間ファクタリングでは、売掛先の承諾を得ることなく売掛金を現金化できますが、登記を行うと法務局で債権譲渡の情報が確認できる状態になるため、間接的にファクタリングの利用が把握されるリスクがあります。
これにより、売掛先との取引関係に影響が出たり、信用面で懸念が生じたりする場合があります。
そのため、登記の必要性と売掛先への影響を事前に検討し、サービス選びや手続き方法を慎重に判断することが重要です。

債権譲渡登記を行う際には、必要な書類を揃え、法務局での申請手続きを適切に進めなければなりません。
ここでは、登記に必要な書類や具体的な手続きの流れについてご紹介します。
債権譲渡登記を行う際には、以下の書類を用意する必要があります。
| 必要書類 | 詳細 |
| 代理権限証書(委任状等) | 代理申請を行う場合に必要。 官庁または公署が作成したものについては、作成後3か月以内のものに限る |
| 取下書 | 登記申請を取り下げる場合に必要 |
| 譲渡人の代表者の資格証明書(登記事項証明書) | 作成後3か月以内のものが必要 |
| 譲渡人の代表者の印鑑証明書 | 登記所が作成したもので、作成後3か月以内のものが必要 |
| 譲受人の資格証明書 | 譲受人が法人の場合:登記事項証明書(作成後3か月以内のもの) 譲受人が自然人の場合:住所を証する書面(住民票の写し) |
| 存続期間が登記の日から50年を超えるときの証明書 | 存続期間が登記の日から50年を超えるときは、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面が必要 |
これらの書類を揃えることで、債権譲渡登記の申請準備が整います。
書類不備があると受理されないこともあるため、事前に内容を確認しておくことが重要です。
債権譲渡登記の申請方法は、書面で行う方法とオンラインで行う方法の2種類があります。
債権譲渡登記を書面で申請する場合、以下の手順で手続きを進めます。
| 手続きの流れ | 詳細 |
| 1.事前準備 | 申請に必要な書類を揃え、場合によってはCD-Rなどの電磁的記録媒体を準備する(事前提供方式を利用する場合は不要) |
| 2.申請書の作成 | 法務局所定の登記申請書に必要事項を記入する |
| 3.申請データの作成 | 登記申請書や添付書面の内容を整理し、提出用のデータを準備する |
| 4.申請データのチェック | 書類やデータに不備がないか内容を確認する |
| 5.添付書面の準備 | 債権譲渡登記に必要な各種証明書や委任状などを添付する |
| 6.チェックリストによる最終確認 | 全ての書類やデータに不備がないか提出前に確認する |
| 7.法務局への提出 | 必要書類とデータを法務局に提出し申請を行う |
なお、登記申請は判決による場合を除き、債権譲渡の譲渡人と譲受人の両者が共同で行う必要があります。
債権譲渡登記は、法務局のオンライン申請システムを利用して手続きを行うことも可能です。
オンライン手続きの主な流れは以下の通りです。
| 手続きの流れ | 詳細 |
| 1.事前準備 | 電子証明書の取得など、オンライン申請に必要な環境を整える |
| 2.オンライン申請データの作成 | 登記申請書や添付書面に対応したデータを作成する |
| 3.オンライン申請データのチェック | 作成したデータに誤りや不備がないかを確認する |
| 4.オンライン申請情報の作成 | 申請人プログラムのオンライン申請情報作成を用いて、オンライン申請情報を作成する |
| 5.オンライン申請データの送信 | 法務局宛に申請データを送信する |
| 6.登録免許税の納付 | オンラインでの申請完了後、登録免許税を納付する |
オンラインで債権譲渡登記を申請する場合、いくつかの制限があります。
たとえば、法定代理人による申請や、登記情報の変更がある場合、存続期間が長い場合などはオンライン申請ができません。
また、印鑑証明書や資格証明書などの必要書面は、紙で持参したり郵送したりして提出することはできないため、オンライン申請で提出可能な電子データ形式にするか、必要に応じて書面申請に切り替える必要があります。
オンラインで債権譲渡登記を申請する場合は、これらの制約を事前に確認した上で手続きを進めましょう。

ファクタリングを安心して利用するためには、取引先となるファクタリング会社選びが非常に重要です。
債権譲渡登記が必須か否か、契約方法、手数料など、会社ごとにサービス内容や条件が異なります。
ここでは、ファクタリング会社選びでチェックすべきポイントをご紹介します。
おすすめのファクタリング会社については下記のコラムで詳しく解説しています。
最適なファクタリング会社が見つかるおすすめ会社25選!選び方も解説
ファクタリング会社を選ぶ際には、債権譲渡登記が必須か確認することが重要です。
2者間ファクタリングでは、売掛先の承諾を得ずに売掛金を現金化できる一方で、債権譲渡登記が必要になるケースがあります。
しかし、債権譲渡登記を行う際には費用や手間がかかるため、必ずしも全ての利用者にとって最適とは限りません。
そのため、債権譲渡登記が必須か否かを事前にファクタリング会社に確認しておくことが大切です。
債権譲渡登記が必須である場合は、取引条件や費用も含めて総合的に判断することが必要です。
ファクタリング会社を選ぶ際には、契約方法の選択肢があるかどうかも重要なポイントです。
前述したように、ファクタリングの契約方法には主に、利用者とファクタリング会社の2者で契約する「2者間ファクタリング」と、利用者・売掛先・ファクタリング会社の3者で契約する「3者間ファクタリング」の2種類があります。
2者間ファクタリングは、売掛先の承諾を得ずに現金化できるため、手続きに時間がかからずスピーディーに資金調達できる点が特徴です。
一方、3者間ファクタリングは売掛先の承諾が必要ですが、ファクタリング会社が売掛先に直接売掛金の存在を確認できるため、ファクタリング会社の未回収リスクが軽減され、2者間ファクタリングと比較して手数料が低くなる傾向にあるのが特徴です。
希望する契約方法に対応できるかどうかを事前に確認しておくことで、取引条件に合った形で売掛金を現金化できます。
ファクタリング会社を選ぶ際には、手数料が相場の範囲内であるかを確認することも重要です。
手数料は契約方法によって大きく異なります。
一般的に、手数料の相場は2者間ファクタリングで8%~18%、3者間ファクタリングで2%~9%となっています。
2者間ファクタリングより3者間ファクタリングの相場が低いのは、先述した通りファクタリング会社の未回収リスクが軽減されるためです。
手数料の差は、実際に手元に入る現金の額にそのまま影響します。
取引条件や売掛金の額に応じて、無理のない手数料で契約できる会社を選ぶことが、安心してファクタリングを利用するためのポイントです。
ファクタリングの手数料については下記のコラムで詳しく解説しています。
ファクタリング手数料はいくら?相場や内訳、費用を抑える方法を紹介!
償還請求権とは、売掛金の売却後に、売掛先が倒産などの理由で支払不能の状態に陥った場合に、ファクタリング会社が利用者に費用を求める権利のことです。
ファクタリングでは、原則として償還請求権なしの契約が結ばれます。
そのため、万が一売掛金が回収できなくても利用者に弁済義務は発生しません。
この仕組みが、ファクタリングを利用する大きなメリットの一つです。
ただし、契約の詳細については事前にファクタリング会社に確認しておくことが重要です。
悪徳な業者の場合、償還請求権ありの契約を提示してくる可能性もあるため、契約の際には「償還請求権なし」が明確に契約書に記載されているかを確認することが安心して利用するポイントです。
償還請求権については下記のコラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要なリスクや注意点を解説
ファクタリング会社を選ぶ際には、公式HPに記載されている会社情報が正確で、信頼できる会社であるかを確認することが重要です。
所在地や代表者名、連絡先、資本金や設立年などの基本情報は、会社の信頼性を判断するための重要な指標となります。
とくにオンラインのみで申し込みが可能なファクタリング会社の場合、情報の正確性が不十分だと、契約後の連絡やトラブル対応に支障が出る可能性があります。
くわえて、過去の取引実績や口コミもあわせてチェックしておくと安心です。
情報が不透明なファクタリング会社は、高額な手数料を提示してくる悪徳業者の可能性もあるため注意が必要です。
その点、正しい情報が公開されている会社であれば、万が一問題が発生した場合にも適切な対応が期待でき、安心してファクタリングを利用できます。
悪徳業者については下記のコラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは違法ではない!その根拠と悪徳業者・優良業者それぞれの特徴を解説

債権譲渡登記については、仕組みや手続方法、費用など、疑問に思う点が多くあります。
ここでは、債権譲渡登記に関する疑問にお答えします。
債権譲渡登記を行う際には、法務局に支払う登録免許税が必要です。
登録免許税の金額は、債権の個数によって異なります。
具体的には、債権が5,000個以下の場合は1件につき7,500円、5,000個を超える場合は1件につき15,000円です。
また、登記手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、さらに費用がかかります。
司法書士報酬は事務所によって異なりますが、一般的には数万円~十数万円程度が相場です。
債権譲渡登記が必要な場合は、これらの費用が追加でかかることを踏まえて、資金計画を立てることが重要です。
基本的には、債権譲渡登記を行っても売掛先に自動的に通知されることはありません。
そのため、売掛先が登記情報を確認しない限り、ファクタリングの利用が知られる可能性は低いといえます。
ただし、登記情報は原則として誰でも閲覧できる公開情報です。
万が一、売掛先が法務局で登記内容を確認すれば、売掛金がファクタリング会社に売却されていることを知ることができます。
将来的な取引関係や信用面を考慮すると、必要に応じて売掛先への説明や事前相談を検討しておくと安心です。
債権譲渡登記は抹消することが可能です。
登記された内容に誤りがあった場合や、債権譲渡の効力が消滅した場合には、抹消登記の手続きを行うことで、登記簿からその記録を削除できます。
抹消登記を行う際には、登記原因証明情報(債権の消滅を証明する書類など)を提出し、登記申請書を作成して法務局に申請します。
申請は書面による方法のほか、オンラインで行うことも可能です。
ただし、抹消登記にも登録免許税がかかります。
手続きが複雑な場合は、司法書士など専門家への依頼も検討すると良いでしょう。
債権譲渡登記が行われても、企業の信用情報には直接影響しません。
債権譲渡登記は、あくまで「債権の譲渡が行われた」という事実を法務局で公示するためのものであり、信用情報機関が管理する「支払いの遅延」や「借入状況」などの信用情報とはまったく別の仕組みです。
そのため、ファクタリングの利用に伴い債権譲渡登記がされたとしても、信用情報や企業の信用スコアに記録されることはありません。
登記自体が信用に悪影響を与えるものではありませんが、売掛先との信頼関係を保つためには、必要に応じて事前に説明しておくと安心です。
信用情報については下記のコラムで詳しく解説しています。
ファクタリングの利用は信用情報に影響する?審査に通過するためのポイントも解説

ファクタリングを検討している事業主にとって、信頼できる会社を選ぶことは非常に重要です。
スピードや手数料だけでなく、契約の透明性やサポート体制など、安心して取引できるかどうかがファクタリング会社を選ぶ大きなポイントとなります。
当機構では、売掛先からの承諾を得ずに売掛金を現金化できる「2者間ファクタリング」と、売掛先の承諾を得て行う「3者間ファクタリング」の両方に対応しています。
そのため、資金ニーズに合わせて最適な契約方法を選ぶことができます。
また、買取可能額に下限や上限を設けておらず、少額から高額の売掛金まで幅広く利用できます。
手数料は業界でも最低水準の1.5%〜となっており、余分なコストを抑えた資金調達が可能です。
透明性の高い料金体系を採用しているため、契約内容に不明点が残ることもありません。
さらに、当機構が提供するオンライン完結型サービス「FACTOR⁺U(ファクトル)」では、申し込みから入金まで最短40分で対応しています。
必要書類は「口座の入出金履歴(直近3か月分)」と「売掛金に関する書類(請求書、契約書など)」の2点のみで、全ての手続きがWeb上で完結します。
来所の必要がないため、急な資金需要にもスピーディーに対応できます。
安心・迅速・柔軟なファクタリングをお求めの方は、ぜひ当機構のサービスをご検討ください。
債権譲渡登記は、債権を譲渡する際、第三者や取引先(債務者)に対して権利関係を明確にするための制度です。
ファクタリングにおいては、主に2者間ファクタリングを利用する際に債権譲渡登記が必要になることがあります。
登記には必要書類の準備や申請手続きが必要で、登録免許税などの費用が発生します。
そのため、登記の必要性や手間、費用を踏まえて、自社の状況に合ったファクタリング会社を選ぶことが重要です。
当機構では、最短即日での入金が可能なファクタリングを提供しており、柔軟な審査を行っております。
また、債権譲渡登記は必須としておらず、手数料も業界最低水準で設定しているため、コストを抑えながら安心して現金を確保できます。
資金繰りに関するご相談も幅広く受け付けておりますので、まずはお気軽に当機構までお問い合わせください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。