

Same day
Procurement
Diagnostics
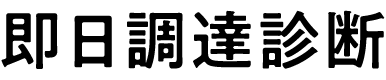
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

M&Aは、企業が成長するための重要な手段となっており、近年では市場の変化に迅速に適応するためにますます活用されています。
今回は、M&Aの基本的な概念や代表的なスキームについてご紹介します。
また、M&Aが買い手と売り手の企業にとってそれぞれどのような目的で行われるのかについてもまとめているので、ぜひご参考にしてください。
【注目】資金繰りでお悩みの事業主様へ
手元資金が足りずお悩みの事業主様へ、売掛金を早期現金化できるファクタリングサービスをおすすめいたします。
当機構では、申し込みから最短30分で審査結果の提示、最短3時間で入金が可能なため、売掛金をスピーディーに現金化することが可能です。
また、当機構は関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」でもあるため、安心してご利用いただけます。
資金繰りでお悩みの事業主様は、この機会にぜひお問い合わせください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。
M&Aは、企業の合併(Merger)や買収(Acquisitions)を指しますが、広義では提携も含まれます。
企業が他の企業と合併・提携することで、事業規模の拡大やシナジー効果を狙う経営戦略の一つです。
近年では、スタートアップの買収によるイノベーションの促進や、グローバル展開の手段としても活用されています。
買収には主に株式取得と事業譲渡のスキームがあります。
株式取得は、譲渡(売却)企業の株式を譲受(買取)し、経営権を獲得する方法です。
対象企業の法人格を維持したまま経営権を得られるため、事業の継続性が高いのが特徴です。
一方、事業譲渡は全ての事業、もしくは特定の事業のみを売買する方法です。
買収側は必要な事業のみを取得でき、売却側は事業を整理できるメリットがあります。
合併は複数の企業を統合し、一つの法人として再編成する手法です。
合併には主に吸収合併と新設合併の2種類があります。
吸収合併は一方の企業が存続し、もう一方の企業が消滅する形態で、存続会社は消滅会社の資産・負債・権利義務を継承します。
新設合併は合併対象の全ての企業を解散させ、新たに設立した企業に統合する手法です。
両社が対等な立場で新会社を設立できるメリットがありますが、法人の新規設立に伴う手続きが必要となります。
提携には資本提携と業務提携の2種類があります。
資本提携は、一方の企業が相手企業の株式を取得したり、両社の株式を持ち合ったりすることにより企業間の関係を強化する方法です。
完全買収には至らず、お互いの独立性を保ちつつ協力関係を構築できます。
業務提携は、資本関係を伴わず、技術・販売・物流などの分野で協力する手法です。
例えば、共同開発、販売網の共有、製造委託などが含まれます。
これにより、企業は互いの強みを活かし、リスクを抑えながら事業拡大を図ることが可能です。
M&Aについては下記コラムで詳しく解説しています。
M&Aとは?その目的やメリット、スキームを解説

M&Aを行う主な目的は以下の通りです。
M&Aによって相乗効果(シナジー効果)を狙うことができます。
例えば、工場や流通網の統合によりコスト削減が可能になります。
また、ブランドや顧客基盤を共有し、売上の拡大を狙うこともできるでしょう。
新たな市場や販路を獲得し、収益向上につなげることも可能です。
その他、買収企業の技術やノウハウを活用し、研究開発の強化や製品の競争力向上を目指すケースもあります。
とくにITや製薬業界では、相乗効果を狙ったM&Aが活発です。
このように、M&Aは単なる企業統合ではなく、相乗効果を生み出し、長期的な成長を実現する手段として活用されています。
M&Aは、企業が市場の変化に適応するための重要な手段として活用されます。
市場環境は、技術革新、消費者ニーズの変化、競争の激化などにより常に変動しており、企業はこれに対応する必要があります。
例えば、デジタル化の進展により、伝統的な企業がIT企業を買収し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させるケースがあります。
また、新たな市場へ進出するために、既存の現地企業を買収し、地域密着型の事業展開を行うケースもあります。
M&Aは市場の変化に柔軟に対応し、成長を持続させるための有効な戦略の一つとなっています。
以下で譲渡(売却)側がM&Aを行う主な目的をご紹介します。
譲渡(売却)側の企業がM&Aを行う目的の一つに、投資回収や現金化の確実性があります。
企業や事業への投資を回収し、資金を確保することで新たな成長戦略に活用し、経営の安定化を図ることができます。
例えば、ベンチャー企業の創業者や投資家は、事業の成長後に大手企業へ売却することで、リターンを得ることが可能です。
M&Aによる売却は、株式市場での上場よりも短期間で現金化できる場合が多く、確実な投資回収手段として選ばれることがあります。
譲渡(売却)側の企業がM&Aを行う目的の一つに、事業承継があります。
とくに、中小企業では後継者不足が深刻化しており、親族や社内に適任者がいない場合、M&Aを活用して事業を存続させるケースが増えています。
M&Aによる事業承継では、経営権を第三者に譲渡することで経営基盤が強化され、事業のさらなる発展が期待できます。
M&Aを行うことで、従業員の雇用やノウハウを残すことができます。
譲渡先企業が従業員を引き継ぎ、事業運営を続ける場合、雇用の安定や給与の継続が保証されます。
これにより、従業員の生活が守られ、また、企業の持つ独自の技術や経験が無駄にされることなく活用されます。
事業のノウハウが売却後も活かされることで、事業の継続性が高まり、売掛先や顧客へのサービスの質が維持されるため、企業の価値を守ることにもつながります。
経営難や業績不振、資金繰りの問題などに直面している企業は、M&Aを通じて他の企業に事業を売却することで、経営危機を乗り越えられる可能性があります。
譲渡先企業が資金援助や経営ノウハウを提供することで、売却側の事業は再生のチャンスを得ることができるでしょう。
また、譲渡によって負債の整理や経営資源の集中が可能になり、事業の継続や従業員の雇用維持も実現できます。
M&Aを通じて企業を売却することで、創業者は事業の成長に投じた資本や時間に対するリターンを確保できます。
この現金化によって、創業者は引退後の生活資金や次の投資機会に資金を充てることが可能です。

譲受(買取)側がM&Aを行う目的は主に以下の3つです。
新規事業の立ち上げには時間とコストがかかり、さらに軌道に乗るまでに時間を要します。
しかし、M&Aを利用し既存の事業を買収することで、短期間で市場に参入し、競争優位性を得ることが可能です。
譲受(買取)側の企業がM&Aを行う目的の一つに、事業規模を拡大することがあります。
既存の事業を買収することで、短期間で売上や市場シェアを拡大でき、競争力を強化できます。
さらに、M&Aにより、新規事業領域に進出したり、地理的な拡大を図ったりすることも可能です。
例えば、海外の企業を買収することで、グローバルな市場に参入し、地域特有の競争力を得ることができます。
M&Aは企業戦略の一環として、事業の拡大やシナジー効果の獲得、迅速な市場参入など、さまざまな目的で活用されます。
譲渡側は事業の継承や投資回収、経営再建を目指す一方で、譲受側は事業規模の拡大や競争力強化、新規事業への参入を狙います。
M&Aを通じて企業は成長を加速させ、市場に柔軟に対応しながら競争優位性を確立していくことができます。
当機構では、資金調達のサポートを行っています。
資金繰りでお悩みの事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。