

Same day
Procurement
Diagnostics
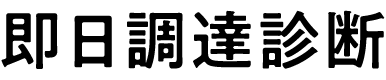
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

事業を営む上で、設備投資や急な支出などによって、運転資金が不足する場面は少なくありません。
そんなときに重要となるのが「資金調達」です。
資金調達を検討する際は、まずは資金が必要になる理由や自分に合った調達手段を理解することが大切です。
今回は、運転資金が必要になる具体的なタイミングや調達額の計算方法、主な資金調達方法などをご紹介します。
また、運転資金の融資を受ける際の審査ポイントについてもまとめているので、ぜひご参考にしてください。
資金調達については下記コラムでも詳しく解説しています。
資金調達とは?代表的な11の方法とメリット・デメリット
【注目】ファクタリングの利用を検討中の方へ
ファクタリングは、資金調達の中でもとくにスピーディーに資金を調達できる金融サービスで、利用するサービスによっては最短即日での資金調達も叶います。
当機構は、関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」なので、ファクタリングの利用が初めての方も安心してご利用いただけます。
また、審査完了まで最短10分、現金の振込まで最短40分で完了するAIファクタリング「FACTOR⁺U(ファクトル)」も提供しているので、ぜひご検討ください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

事業を継続・成長させる上で、運転資金の確保は欠かせません。
売上が立っていても、仕入費用や人件費、家賃などの固定費は継続的に発生するため、資金繰りが厳しくなることもあります。
とくに、売掛先からの入金が遅れる場合や、新たなビジネスチャンスに対応するために仕入量を増やす場面などでは、手元の現金だけでは補いきれないケースもあるでしょう。
そのような場合に、必要なのが外部からの資金調達です。
以下では、運転資金の調達が必要なケースと調達額の計算・目安をご紹介します。
運転資金の調達が必要なケースは以下の通りです。
売掛先に商品やサービスを提供した後、一定期間後に代金を受け取る掛取引を行っている場合、実際にサービスや商品を提供してから現金が手元に入るまでに時間差が生じます。
しかし、この間にも仕入れや人件費、家賃などの支払いは発生するため、帳簿上は利益が出ていても現金が不足することがあります。
とくに売上規模が急拡大している時期には、売掛金の額も増加し、資金繰りがより厳しくなることもあるでしょう。
こうした状況では、売掛金の入金を待たずに、運転資金を確保するための資金調達を検討する必要があります。
事業拡大や物価上昇、人件費の高騰などにより、固定費や仕入原価が増加すると、毎月の支出が膨らみ、手元の現金が不足するリスクが高まります。
黒字経営であっても、現金が足りなければ日々の経費の支払いに支障をきたす可能性があるでしょう。
こうした状況では、一時的に運転資金を調達し、安定した経営を維持することが求められます。
事業には季節や時期特有の要因によって一時的に現金が不足することがあります。
具体的には、繁忙期前に在庫を多く仕入れる必要がある場合や、賞与・年末調整など一時的に人件費が増加する時期などがあり、多額の支出が先行します。
また、閑散期には売上が減少し、通常よりも現金収入が落ち込むこともあるでしょう。
こうした一時的な資金需要に備えるためには、必要な時期に適切に運転資金を調達し、事業活動に支障が出ないようにすることが重要です。
景気の変動や競合の影響、取引の減少などにより売上が悪化すると、事業の収入が減少し、手元の現金が不足する事態に陥ることがあります。
売上が落ち込んでも、家賃や人件費、光熱費などの固定費は継続的に発生するため、資金繰りが厳しくなります。
とくに急激な売上減少があった場合には、短期的な対応が求められます。
このような状況では、事業の立て直しを図るためにも、早めに運転資金を調達し、資金繰りの安定を確保することが重要です。
新たな事業展開や業務効率化のために設備投資を行う場合、一時的に多額の現金が必要になります。
例えば、工場の機械更新や店舗の改装、新システムの導入などは、将来的な売上や生産性の向上につながる一方で、初期費用としてまとまった支出が発生します。
このような投資を貯蓄だけで賄おうとすると運転資金が圧迫され、日々の事業運営に支障をきたす恐れがあります。
安定した経営を維持しつつ投資を実現するためには、運転資金の調達が必要です。
適切な運転資金を確保するためには、まず自社の事業活動に必要な現金の流れを把握し、具体的な金額を算出することが重要です。
一般的に、必要な運転資金は以下の計算式で求めることができます。
| 運転資金 = 売掛債権 + 棚卸資産 - 買入債務 |
棚卸資産とは、販売や製造のために企業が保有している資産のうち、まだ販売されていない在庫のことを指します。
月商にかけて運転資金を算出する方法は以下の通りです。
| 運転資金 = 平均月商 ×(売掛債権回転期間 + 棚卸資産回転期間 - 買入債務回転期間) |
平均月商は会社の月あたりの売上規模のことで、「年間売上高 ÷ 12」で求めることができます。
上記の式で計算し、運転資金がマイナスになった場合は現金が不足していることを意味します。
そのため、早めに資金調達を検討しましょう。
一般的に、必要な運転資金の目安は「月商の3か月~6か月分」とされています。
この目安は売掛金の回収期間や在庫の保有期間、支払サイトなどを加味した上で、事業運営に必要な資金の平均的な数値です。
なお、業種や取引条件によって必要な運転資金は変動するため、自社の状況に応じて計算することが大切です。
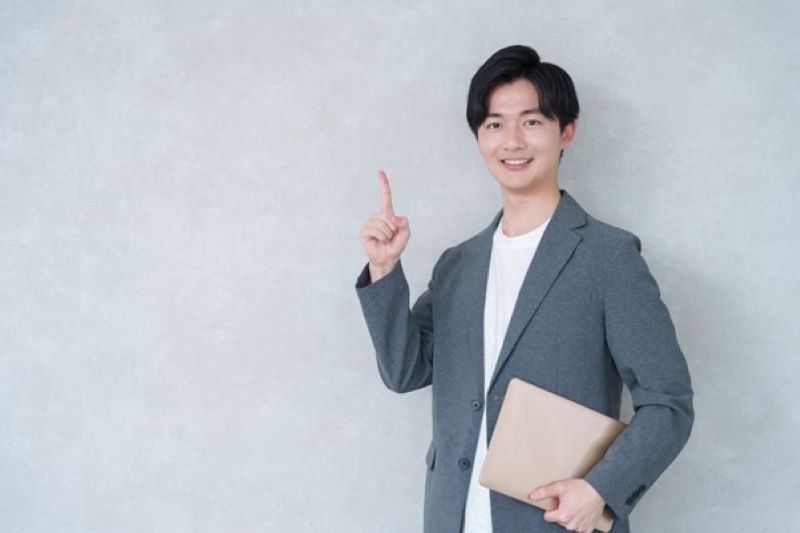
運転資金を調達する際には、さまざまな金融機関から融資を受けることができます。
以下で運転資金の融資が受けられる金融機関をご紹介します。
日本政策金融公庫は、政府系金融機関として、主に中小企業や個人事業主向けに運転資金の融資を提供しており、民間の金融機関が融資を行いにくい企業に対しても、低金利で融資を行うことを目的としています。
とくに創業支援や事業継続支援に力を入れており、経済的な困難を抱える企業に対して柔軟な融資条件を提供してくれるのが特徴です。
日本政策金融公庫は創業資金や設備投資資金、運転資金など、さまざまな資金調達の選択肢を提供しており、審査基準も比較的柔軟で、融資の利用がしやすい点が魅力です。
信用金庫や信用組合は、地域密着型の金融機関で、主に中小企業や個人事業主向けに運転資金の融資を行っています。
これらの金融機関は、地域経済の活性化を目指しており、融資の際にも柔軟な対応をすることが多い傾向にあります。
また、金利が比較的低めであることが多く、企業にとってはコスト面でのメリットもあります。
ただし、融資条件や審査基準は信用金庫や信用組合によって異なるため、事前に十分な相談と確認が必要です。
多くの自治体では、地域経済の振興を目的に、低金利での融資や、補助金・助成金制度を提供しており、地域に根ざした事業に対して積極的に支援しています。
融資の条件や金額、返済期間などは自治体ごとに異なり、特定の事業分野や地域の課題解決を目的とした制度も存在します。
また、地方自治体の融資制度は審査基準が比較的柔軟なため、民間金融機関からの融資が難しい企業にとって有力な資金調達手段となります。
地方自治体の融資制度を利用する際は、自治体のホームページや商工会議所で詳細を確認してから手続きを行いましょう。
ノンバンクとは、銀行以外の金融機関で、融資を専門に行っている企業や機関のことです。
運転資金の融資を行うノンバンクは、銀行と比べて審査が比較的迅速で、融資基準が柔軟である傾向にあります。
そのため、急な資金需要に対応しやすい点が特徴です。
ただし、ノンバンクは金利が高くなる傾向にあるため、慎重に比較検討することが重要です。
民間の銀行は、運転資金の融資を行う主要な金融機関であり、幅広い中小企業や個人事業主に対して資金を提供しています。
民間銀行は、審査が厳しく企業の信用力や財務状況を重視する一方で、融資額や条件が明確で金利も比較的安定しているのが特徴です。
一般的に、借入金利は経済動向や政策金利に連動しており、銀行ごとに異なる金利プランが提供されています。
また、運転資金に特化したローン商品や、短期・長期融資を選択できる場合も多く、事業のニーズに合わせた融資を受けることが可能です。

運転資金の調達で融資を受ける場合、審査ポイントを把握しておくことで融資が受けられる可能性が高まります。
運転資金の融資を受ける際には、資金使途を明確に示すことが重要です。
金融機関は融資の審査において、借入金が具体的にどのような使途に使われるのかを重視します。
例えば、「仕入資金として○○万円」「人件費として○○万円」といった具体的な内訳を提示することで、資金計画の信頼性が高まり、審査通過の可能性が上がります。
曖昧な使途や抽象的な表現では計画性に欠けると判断される恐れがあるため、事前にしっかりと資金使途を整理しておくことが求められます。
運転資金の融資を受ける際は、しっかりとした事業計画書を準備することが信頼獲得の第一歩です。
金融機関は、融資先の返済能力や事業の成長性を審査で見極めるために、今後の売上の見通しや市場動向、収支計画といった情報を重視します。
収益モデルや競合との差別化ポイント、具体的な販促戦略などを盛り込み、現実的で実行可能な計画であることを伝えましょう。
過去の業績や顧客数などの実績データを添えることで、さらに信憑性が高まります。
運転資金の融資を受ける際には、一定の自己資金を用意していることが審査においてプラス要素となります。
自己資金とは事業主が自ら準備した現金のことで、金融機関は自己資金を「返済に対する責任感」や「事業への本気度」の指標として見ています。
全額を借り入れで賄おうとするよりも、自己資金で一部を賄っているほうが、返済能力や計画性があると判断されやすくなります。
とくに創業時や赤字決算の状況下では、自己資金の有無が審査結果を左右することもあるため、融資申請前には可能な範囲で自己資金を用意しておくことが重要です。
運転資金の融資を申し込む際には、必要書類を正確かつ不備なく準備することが大切です。
金融機関は提出された書類をもとに事業の状況や信用力を判断するため、書類の不備や記載ミスがあると、審査に時間がかかったり、最悪の場合は審査に通らなかったりすることもあります。
一般的に必要とされるのは、直近の決算書、確定申告書、事業計画書、資金使途の明細、身分証明書などです。
書類の整合性や最新の情報が反映されているかどうかも重要なポイントとなります。
スムーズな融資手続きを行うためにも、事前に必要書類をリストアップし、丁寧に準備しておきましょう。

運転資金の調達手段には、「ビジネスローン」「補助金・助成金」「ベンチャーキャピタルからの投資」「クラウドファンディング」「親族・友人からの借り入れ」などもあります。
以下に詳細を記載いたします。
ビジネスローンは、銀行以外の金融機関やノンバンクが提供する事業者向けの融資商品で、比較的スピーディーに運転資金を調達できる手段のひとつです。
審査期間が短く、必要書類も少ない場合が多いため、急な資金ニーズに対応しやすい点が特徴です。
ただし、一般的に銀行融資よりも金利が高く設定される傾向があるため、返済計画をしっかり立てた上で利用することが重要です。
補助金や助成金は原則返済の必要がない資金調達手段で、主に国や地方自治体が提供しています。
創業支援や設備導入など、目的に応じたさまざまな制度があり、補助金や助成金の申請には事業計画書や実施内容の報告、審査が必要です。
補助金や助成金をうまく活用すれば財務の安定に寄与しますが、交付までに時間がかかるため、計画的な申請が重要です。
ホームページで定期的に公募情報をチェックし、自社の事業に合った補助金・助成金の活用を検討しましょう。
補助金・助成金については下記コラムで詳しく解説しています。
助成金と補助金の違いをわかりやすく解説!管轄・予算・給付額・期間の相違点とは
ベンチャーキャピタルとは、成長が見込まれる未上場企業やスタートアップ企業に対して、資金を出資する投資会社や投資家のことを指します。
将来の成長や利益を見込んで企業に出資を行うため返済の必要はありませんが、ベンチャーキャピタルからの投資を受けることで、企業の株式の一部を譲渡する必要があります。
そのため、経営権や意思決定にベンチャーキャピタルが関与する場合もあることは念頭に置いておきましょう。
クラウドファンディングは、インターネットを通じて多数の人から現金を募る方法で、新商品や新サービスの開発、地域活性化プロジェクトなど、特定の目的に向けた資金調達手段として活用されています。
支援を募るテーマはさまざまですが、共感を得られる内容であれば、多くの支援を集めやすいという特徴があります。
クラウドファンディングの形式には、支援者に返礼品を提供する「購入型」や、出資を受ける「投資型」などがあり、プロジェクトの内容に応じて選ばれます。
金融機関の融資とは異なり、信用力よりも企画内容や社会的意義が重視されるため、独自性のあるアイデアを持つ事業主にとって有効な資金調達方法といえます。
クラウドファンディングについては下記コラムで詳しく解説しています。
クラウドファンディングとは?メリットやデメリットは?成功事例などをご紹介
親族や友人からの借り入れは、比較的柔軟な条件で運転資金を調達できる手段の一つです。
利息や返済期間について相談しやすく、信用力や事業実績が乏しい創業初期などでも現金を得られる可能性があります。
ただし、金銭のやり取りは人間関係に影響を及ぼすリスクがあるため、口約束ではなく、借用書を作成し返済計画を明確にすることが大切です。

運転資金の調達手段として、ファクタリングもあります。
ファクタリングとは、未入金の売掛金をファクタリング会社に売却して現金化するサービスのことです。
通常、売掛金が入金されるまで1か月〜数か月ほどかかりますが、ファクタリングを利用することですぐに現金化できます。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
ファクタリングの契約方法には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2つがあります。
2者間ファクタリングでは「利用者」と「ファクタリング会社」の2者間で取引を行います。
売掛先に承諾を得る必要がないため、スピーディーに資金調達を行えるのが特徴です。
ただし、2者間ファクタリングではファクタリング会社が売掛先に直接売掛金の存在を確認できず未回収リスクが高いため、3者間ファクタリングに比べて手数料が高くなります。
2者間ファクタリングの手数料相場は、8%~18%です。
3者間ファクタリングでは、「利用者」「ファクタリング会社」「売掛先」の3者間で取引を行います。
2者間ファクタリングと異なり、売掛先から承諾を得られない場合はファクタリングの利用はできません。
そのため、2者間ファクタリングよりも利用のハードルが高くなりますが、ファクタリング会社が売掛先に直接売掛金の存在を確認でき未回収リスクが低くなることから3者間ファクタリングの手数料は2者間ファクタリングと比較し低くなる傾向にあります。
3者間ファクタリングの手数料の相場は、2%〜9%です。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
ファクタリングは最短で即日現金化が可能なサービスもあり、急な資金ニーズにも対応しやすいのが特徴です。
また、借り入れではないため負債として計上されず、信用力にも影響を与えない点は企業にとって大きなメリットになるでしょう。
さらに、売掛金をファクタリング会社に売却することで、万が一の未回収リスクを軽減できる点も大きな魅力です。
とくに、売掛先の経営状況に不安がある場合や、売掛金が入金されるまでに時間がかかる業種ではファクタリングを利用することが大きなメリットとなります。
くわえて、ファクタリングでは利用者自身の財務状況よりも、売掛先の信用力が審査のポイントとなるため、赤字決算や創業間もない事業主でも活用しやすいというメリットがあります。
事業を安定して続けていくためには、必要な資金を確保することが欠かせません。
しかし、資金調達には返済などの負担があるため、目的や金額をはっきりさせた上で、自社に合った方法を選ぶことが重要です。
当機構は、ファクタリングをはじめとした多様な資金調達手段に精通しており、事業主様のニーズに応じた資金調達のサポートを行っています。
また、AIファクタリングサービス「FACTOR⁺U(ファクトル)」も取り扱っており、入金まで最短40分で行うことができます。
運転資金を調達したい事業主様は、ぜひこの機会にご利用ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。