

Same day
Procurement
Diagnostics
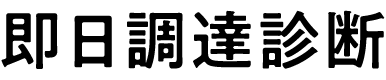
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

資金の状況を把握することは、企業活動において欠かせません。
きちんと把握できていない場合、資金繰りがうまくいかなくなる可能性があるだけでなく、最悪の場合は倒産の恐れもあるかもしれません。
企業活動における資金の状況を細かく把握するためにも、キャッシュフローについて理解しておきましょう。
そこでこの記事では、キャッシュフローについて解説するとともに、キャッシュフロー計算書の詳細や作成方法などをご紹介します。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

キャッシュフローとは、企業活動をする上で生じるお金(キャッシュ)の流れ(フロー)のことです。
企業会計では、企業にお金が入ってくることを「キャッシュ・イン・フロー」、企業からお金が出ていくことを「キャッシュ・アウト・フロー」といい、この2つをまとめて「キャッシュフロー」といいます。
キャッシュフローで扱うのは、基本的に現金のみとなっています。
一定期間内にどれだけの現金が入ってきて、どれだけの現金が出て行ったのか、お金の動きを可視化するものです。
キャッシュフローについては下記コラムで詳しく解説しています。
経営を安定化し成長を促進する「キャッシュフロー」について
キャッシュフローを把握することは、会社の現状を知る上で重要となります。
以下では、キャッシュフローを把握する重要性について解説します。
キャッシュフローを把握することは、企業の資金繰りの悪化を防止するために不可欠です。
キャッシュフロー計算書では収益性だけでなく、実際の現金の動きを確認できます。
これにより、資金繰りの悪化を防ぎ、必要なときに適切な資金調達や支出の見直しが可能になります。
キャッシュフロー計算書を通じて現金の流入と流出を詳細に分析することで、企業の財務健全性や収益性を正確に評価できます。
これにより、どの事業やプロジェクトが利益を出し、どの活動が資金を消費しているかを明確に把握できます。
経営者は、キャッシュフローの状況をもとに投資やコスト削減、資金調達などの具体的な戦略を立案し、企業の持続的成長を支えるための適切な意思決定を行うことが可能です。
なお、キャッシュフロー計算書は「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」の3つに区分されています。
詳しくは後述します。
キャッシュフローを把握することで、安定した現金管理が可能となります。
これにより、金融機関に対して健全な財務状況を示すことができ、信頼性が増すため、資金調達が円滑に進みます。
とくに安定した営業活動によるキャッシュフローは、企業の信頼性と経営の安定性を証明する要素となります。つまり、キャッシュフローの把握は企業の信用力を強化し、長期的な成長を支える基盤となるのです。

キャッシュフローを把握する上で欠かせないのが「キャッシュフロー計算書」。
営業活動などの企業の活動を「営業取引」「投資取引」「財務取引」の3つに分けて、お金の動きを示したものです。
ここで確認できるのは、基本的に現金の動きのみ。
この現金には、ほぼ現金として扱う普通預金や当座預金、定期預金、公社債投資信託などは含みますが、換金が難しく価値が変動しやすいものについては含みません。
企業の活動は現金がないと行うことができませんが、取引で現金を扱うことは少なく、そのほとんどを月末にまとめて支払う買掛金や売掛金で対応しています。
そのため、もし掛取引で商品を販売した場合、損益計算書には売上と記載しますが、実際には月末に代金を振り込んでもらうまで会社に現金は入ってきておらず、ズレがある状態。
キャッシュフロー計算書は、このズレがどれくらいあるかを把握するためのものです。
つまり損益計算書を見ても実際に売掛金が入ってきているのかまでは確認できませんが、キャッシュフロー計算書を確認することで、まだ入金されていないお金がどこにどれくらいあるのかを一目で確認することができるのです。
キャッシュフロー計算書は、企業の資金の状況を把握するのに非常に重要なものですが、すべての会社に作成義務があるわけではありません。作成義務があるのは金融商品取引法が適用される上場企業などに対してで、中小企業や個人事業主は義務化されていないのです。
しかし、キャッシュフロー計算書を作成することで、「資金不足になっていないか把握することができる」「粉飾が難しいことから資金調達の評価に活用できる」というメリットが得られます。
このことから、作成義務の有無にかかわらずキャッシュフロー計算書を作成して、流れを把握しておくのがおすすめです。
キャッシュフロー計算書については下記コラムで詳しく解説しています。
なぜ重要?キャッシュフロー計算書の見方を解説
キャッシュフロー計算書は以下3つの項目に分かれています。
営業活動によるキャッシュフローとは、主に本業の営業活動によって生じたキャッシュの増減のこと。
例えば、現金での売上や現金で回収した売掛金はプラス、現金での仕入れや現金で支払った買掛金、給料、経費などはマイナスとして計上します。
基本的に本業に関わる現金の動きが基準となります。
つまり、この項目がマイナスになっている場合、本業での収支がマイナスであることを表します。
投資活動によるキャッシュフローとは、将来的な利益獲得や資産運用を目的とした投資活動によって生じたキャッシュの増減のこと。
つまり、設備投資や余剰資金の運用による現金の流れを表します。
例えば、有価証券や有形固定資産の売却による現金収入をプラス、有価証券や有形固定資産を取得したことによる現金支出をマイナスとして計上します。
現状を維持したり将来へ投資したりするために、現金がどれくらい出入りしているのかを確認できるのです。
財務活動によるキャッシュフローとは、資金調達や受けた融資の弁済、配当金の支出など、投資活動・営業活動を継続するための財務活動によって生まれるキャッシュの増減のこと。
つまり、資金調達や融資で得たお金に関する現金の流れを表します。
例えば、借入金による現金収入、社債や株式を発行したことによる現金収入などをプラス、借入金返済や社債償還による現金支出、配当金の支払いによる現金支出などはマイナスとして計上します。
この項目をチェックすれば、資金調達の状況が判断できるのです。
フリーキャッシュフローとは、企業が自由に使えるキャッシュのこと。
フリーキャッシュフローの計算式は以下の3つです。
| ①(営業活動によるキャッシュフロー)+(投資活動によるキャッシュフロー) =フリーキャッシュフロー ②(営業活動によるキャッシュフロー)−(設備投資額) =フリーキャッシュフロー ③(税引き後営業利益)+(減価償却費等償却額)−(設備投資額)±運転資本増減額 =フローキャッシュフロー |
フリーキャッシュフローの有無や金額から、投下資金がしっかり回収できているか、事業成長のための投資余力があるかなどが分かります。
上場企業などに作成義務がある財務諸表のうち、キャッシュフロー計算書と貸借対照表、損益計算書は「財務三表」といいます。
なかでもキャッシュフロー計算書は、財務管理が適切に行われているかを判断するもの。
貸借対照表と損益計算書と比較することで、より細かく経営状態を分析することができるのが特徴です。
貸借対照表は、期末時に会社にどれくらいの資産があるかを示したものです。
資産と負債を管理して税務状況を把握する目的で作成します。
キャッシュフロー計算書にある「営業活動によるキャッシュフロー」の動きは、貸借対照表の流動資産や流動負債に一致し、「投資活動によるキャッシュフロー」の動きは、貸借対照表の固定資産や投資有価証券に一致します。
さらに貸借対照表の現金・預金の合計額と、キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物はほぼ一致するようになっています。
このほか、キャッシュフロー計算書では、前期から現金が増加している場合、営業活動によるものか借り入れによるものか分かるようになっています。
つまり、現金の動きを一定期間で区切って計算したものがキャッシュフロー計算書、一定期間の期末時に資産と負債の状況を示すのが貸借対照表です。
損益計算書は経営成績を示したもので、売上と費用を管理する目的で作成します。
というのも、キャッシュフロー計算書が一定期間の現金の動きを表しているのに対して、損益計算書は一定期間の売掛金や買掛金を含む会社の経営状況を表しています。
そのため、損益計算書では利益を確認することはできますが、実際に動いた現金額については把握することができません。
つまり、もし損益計算書で利益が出ているのにもかかわらずキャッシュフロー計算書で赤字となっている場合、売掛金の回収が遅れている可能性があるのです。
このように、キャッシュフロー計算書は損益計算書を補完する役割があります。

では、キャッシュフロー計算書から会社の状態はどのように見えるのでしょうか。
8つのタイプに分けて解説します。
| タイプ | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |
| 健全型 | + | − | − |
| 積極型 | + | − | + |
| 安定型 | + | + | + |
| 救済型 | − | + | + |
| 改善型 | + | + | − |
| 勝負型 | − | − | + |
| リストラ型 | − | + | − |
| 大幅見直し型 | − | − | − |
営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがマイナスの会社は、「健全型」に分類されます。
健全型は本業から十分な収入があり、それを設備投資や借り入れの返済に充てている状態です。
順調な事業経営ができているといえるでしょう。
営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがプラスの会社は、「積極型」に分類されます。
積極型は、本業で現金を増やした上で、金融機関からの借り入れで積極的に設備投資を行っている会社であることが分かります。
営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローもプラス、財務キャッシュフローもプラスの会社は、「安定型」に分類されます。
安定型は本業からの十分な収入はあるものの、設備投資には積極的ではない状態です。
手元資金を重視している傾向にあるといえるでしょう。
営業キャッシュフローがマイナス、投資キャッシュフローがプラス、財務キャッシュフローがプラスの会社は、「救済型」に分類されます。
救済型は、本業でのマイナスを資産売却や借入金で補填している状態です。
資金繰りが深刻であるといえます。
営業キャッシュフローと投資キャッシュフローがプラス、財務キャッシュフローがマイナスの会社は、「改善型」に分類されます。
改善型は本業と資産売却で得た資金を返済に充てており、財務状況の改善を図っている状態であると考えられます。
営業キャッシュフローと投資キャッシュフローがマイナス、財務キャッシュフローがプラスの会社は、「勝負型」に分類されます。
勝負型は本業での収入がマイナスにもかかわらず、設備投資や借り入れなどを行い、積極的に勝負している会社であることが分かります。
営業キャッシュフローがマイナス、投資キャッシュフローがプラス、財務キャッシュフローがマイナスの会社は、「リストラ型」に分類されます。
リストラ型は本業で十分な収入が得られず、資産を売却して借入金を返済している状態にある会社です。
営業キャッシュフロー・投資キャッシュフロー・財務キャッシュフローのすべてがマイナスの会社は、「大幅見直し型」に分類されます。
大幅見直し型は本業が厳しいにもかかわらず、財務キャッシュフローもマイナスとなっているため、大幅な見直しが必要である状態です。

キャッシュフロー計算書には、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローがあると解説しました。
このうち、営業活動によるキャッシュフローは、直接法と間接法の2種類で表すことができます。
どちらを利用しても営業活動によるキャッシュフローの金額は同じなので、内容を確認した上でどちらが利用しやすいかを判断すると良いでしょう。
直接法は、営業活動によるキャッシュフローの流れを総額で考える方法です。
つまり、主要な取引ごとの総額を記載して、より細かく流れを把握することができます。
営業活動における現金の増減には、商品の販売や仕入れ、経費の支払い、給料の支払いなどがありますが、直接法ではこれらの取引ごとにキャッシュフローを総額で表します。
商品の販売による収入と仕入れによる支出は相殺するべきだと考える方もいますが、直接法では相殺せずに表示するのが特徴です。
営業活動に関係するキャッシュフローをすべて記載するため、流れを把握しやすいのがメリットとなっています。
ただし、直接法を利用する場合は必要になる資料が多いため、取引が多い企業ほど作成に時間がかかるのが難点です。
なお、直接法は主に以下の項目で作成します。
| 【支出】 ・給料の支払いによる支出 ・経費の支払いによる支出 【収入】 ・商品の販売による収入 ・商品の仕入れによる支出 |
間接法は、損益計算書をもとにして営業活動によるキャッシュフローを計算する方法です。
簡単にいうと、現金の動きに関することだけを計算する方法となっています。
損益計算書における税引前当期純利益から、各費用の収益を増減して作成します。
損益計算書は収益と費用から構成されていますが、一部キャッシュを伴わないものやタイムラグが生じるものもあります。
このほか、投資活動や財務活動に含まれるものは省き、売掛金や買掛金などについても調整を行います。
このように、税引前当期純利益から調整項目を加減することで、営業活動に関係のあるキャッシュフローを計算するのです。
なお、間接法は以下の項目で作成します。
| 【損益計算書より】 ・税引前当期純利益 ・減価償却費 ・有価証券評価損 【貸借対照表より】 ・売掛金の増減 ・棚卸資産の増減 ・買掛金の増減 |
直接法と間接法を比較すると以下のようになります。
| 直接法 | 間接法 | ||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 営業収入 | 515,000円 | 税引前当期純利益 | 70,000円 |
| 仕入れ代金の支払い | − 300,000円 | 減価償却費 | 20,000円 |
| 人件費支出 | − 100,000円 | 引当金の増減 | 5,000円 |
| 支払利息 | − 5,000円 | 売掛金の増加 | − 10,000円 |
| 法人税等支払 | − 10,000円 | 買掛金の増加 | 5,000円 |
| その他の営業支出 | − 15,000円 | 在庫の増加 | − 5,000円 |
| 営業活動による現金の純増減 | 85,000円 | 営業活動による現金の純増減 | 85,000円 |

直接法と間接法ではキャッシュフロー計算書の作り方が異なります。
以下では、それぞれのキャッシュフロー計算書の作り方をご紹介するので、ぜひご参考にしてください。
直接法のキャッシュフロー計算書の作成手順は以下のようになります。
総勘定元帳などを用意して、下記の金額を集計します。
営業収入に含めるのは、売上にかかわる現金の増加額のみです。
総勘定元帳などから、下記の金額を集計します。
製造業なら商品の仕入れと同じように、原材料にかかわる現金の支出も集計します。
給料や賞与などの人件費の科目のうち、現金で支払った額を集計します。
未払い分があれば差し引いて、純粋な現金支払い分だけを計算しましょう。
損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれる未払い分を差し引いた、当期に現金で支払った分を集計します。
営業支出まで計算したら、直接法による営業キャッシュフローの小計が分かります。
その後は、営業活動・投資活動・財務活動によるそれぞれのキャッシュフローを増減し、当期の増減に前期の現金残高を加えると、当期の現金残高が計算できます。
間接法のキャッシュフロー計算書の作成手順は以下のようになります。
損益計算書を用いて営業キャッシュフローの小計を算出します。
損益計算書の税引前当期純利益の項目を確認し、その金額をキャッシュフロー計算書に入力します。
非資金損益項目とは、キャッシュの増減を伴わない収益のことで、減価償却費や貸倒引当金の当期繰入額のことを指します。
減価償却費はキャッシュが減少するわけではないため、キャッシュフロー計算書では加算します。
貸倒引当金は前期から増加していれば加算、減少していれば減算しましょう。
営業外の損益とは、通常の業務活動とは直接関係のない費用や収益を指します。
具体的には、受取利息や支払利息などが挙げられます。
これらはキャッシュフロー計算書で現金の流れを反映させるために調整されます。
前期と当期の貸借対照表を確認しながら、営業活動におけるキャッシュの増減を計算します。
前期と当期の増減を計算して、売上債権や棚卸し資産の増加はマイナス、減少はプラス、仕入れ債務の増加はプラス、減少はマイナスで調整したら完了です。
資金繰り表とは、企業の現金の入出金を予測するために作成する管理表のことです。
ここでは、資金繰り表の必要性やキャッシュフロー計算書との違い、資金繰り表を作成するメリット、作成方法をご紹介します。
資金繰り表が必要な理由は、将来の資金不足を事前に予測するためです。
一般的に行われる掛取引では、売上の計上と入金のタイミングにズレが生じます。
そのため、売上があっても手元の資金が不足している場合は、資金ショートを引き起こしてしまう可能性があります。
資金繰り表を作成しておけば予測される資金不足に対して事前に対策を講じることができるため、突然の資金ショートによる事業運営の停滞を防ぐことが可能です。
資金繰り表とキャッシュフロー計算書の大きな違いは「活用方法」です。
資金繰り表は、短期間の現金収支を詳細に把握するためのツールです。
日次、週次、または月次単位で作成され、企業の日々の現金の流入と流出を明確にします。
キャッシュフロー計算書は、企業の一定期間の現金の流れを把握するための財務諸表です。
四半期や年度と、長期で作成されます。
このほか、資金繰り表とキャッシュフロー計算書は「詳細度」も異なります。
資金繰り表は詳細な現金収支を記録するのに対し、キャッシュフロー計算書は現金の用途を詳細に記録しません。
このように、資金繰り表とキャッシュフロー計算書はまったくの別物であるため、どちらも作成が必要といえます。
資金繰り表を作成するメリットは主に以下の3つです。
資金繰り表は日々の現金の収入と支出を詳細に記録して可視化できるため、なぜ資金不足になっているかを具体的に特定することが可能です。
仕入れコストが増加した、過剰な在庫を抱えている、予期しない支出が発生したなど、さまざまな要因を見極めることができ、適切な対策を講じることが可能になります。
このほか、売掛先から売掛金の入金が遅れている場合も資金不足に陥る要因です。
資金繰り表を作成していれば金額や時期も明確にできるため、催促をしたり支払い条件を交渉したりと、すぐに次のアクションに移すことが可能です。
資金繰り表は、将来の収入と支出を詳細に計画することができるツールです。
資金不足を事前に予測できるため、突然の資金ショートを防ぎ、企業の安定した運営を確保できます。
資金ショートを予測した場合の対処法には以下が挙げられます。
1つ目が「買掛金の支払いを先延ばしにする」です。
買掛金の支払いを計画的に先延ばしにすることで、キャッシュフローのバランスを取ることができます。
収入が増えるタイミングに支払いを合わせることで、資金不足を防げるでしょう。
ただし、買掛金の支払いを先延ばしにする場合、取引先との信用関係に影響を与える可能性があります。
経営状態が悪いと判断されると取引を停止される可能性があるため、リスクを考慮した上で選択することが望ましいといえます。
2つ目が「ファクタリングサービスの利用」です。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却する資金調達方法です。
売掛金が入金される前に資金調達ができるため、資金繰りの改善に役立ちます。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
資金繰り表を作成することで一定期間内の現金収支のバランスを確認でき、企業が健全な財務状態にあるかどうかを判断できます。
これにより、経営者は適切な戦略を立てることが可能です。
加えて、資金繰り表を活用することで新規プロジェクトや設備投資のタイミングを見極めることもできます。
資金不足になりそうなタイミングを避けて実施できるため、資金ショートを防ぐことが可能です。
このように、資金繰り表は経営の効率化を図り、収益性を向上させるための判断材料として役立ちます。
資金繰り表を作成する場合、「日次の日繰り表」と「月次の資金繰り表」の2種類のフォーマットを用意するのがおすすめです。
フォーマットに決まりはありませんが、一般的には下記の項目を記入します。
| 項目 | 内容 |
| 繰越残高 | 前月から繰り越された預金額を記入します |
| 経常収支 | 営業活動で発生する収支の予測値を記入します |
| 財務収支 | 財務や投資活動で発生する収支を記入します |
| 翌月への繰越 | 月末の預金額を記入します |
資金繰り表のフォーマットはインターネット上で検索するとテンプレートを用意しているサイトが出てくるので、そちらを参考に自社用を作成すると良いでしょう。
資金繰り表については下記コラムで詳しく解説しています。
将来の予測が重要!資金ショートを防ぎ適切な投資を行うための資金繰り
企業活動において、資金の状況を把握することはとても重要です。
利益を上げるためにも、貸借対照表や損益計算書に加えてキャッシュフロー計算書も積極的に活用し、経営状況をより細かく分析していきましょう。
日本中小企業金融サポート機構では、売掛金の未回収リスクを軽減することでキャッシュフローの改善につなげるファクタリングを行っています。
キャッシュフローがうまく可視化できずお困りの方は、ぜひご相談ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。