

Same day
Procurement
Diagnostics
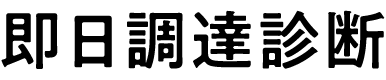
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

補助金や助成金は、原則として返済不要の資金調達手段であり、中小企業では資金繰りを健全に保つために活用するのがおすすめです。
とくに、資金繰りが悪化しやすいとされている建設業では、将来への投資や社内の状況を改善するために役立てられるシーンが多くあります。
そこで本記事では、建設業を営んでいる事業主様に向け、補助金・助成金の特徴やおすすめの制度についてご紹介します。
資金繰りを改善し事業を拡大していくために、ぜひご活用ください。
【注目】資金繰りでお悩みの事業主様へ
早期に資金調達を行いたい場合は、売掛金を売却して現金化するファクタリングが非常に有効です。
ファクタリングを利用すると、最短で即日の資金調達が可能となり、急な支払ニーズや資金繰りの改善に大いに貢献します。
例えば、新規のプロジェクトに着手する際、予期せぬ経費が発生する場合などに迅速に対応できるため、事業の安定化に寄与します。
当機構では、申し込みから最短30分で審査結果の提示、最短3時間で入金が可能なファクタリングサービスをご提供しています。
必要な支払いが迫っている場合でも、柔軟な対応が可能です。
また、関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」であるため、長期的な資金繰りの改善についてもご相談を受け付けています。
資金繰りでお悩みの事業主様は、この機会にぜひお問い合わせください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

補助金や助成金は、国や自治体が企業や個人事業主の経営を支援するために提供する資金のことで、どちらも原則返済の必要がないため、資金調達の手段として非常に有効です。
ただし、補助金と助成金にはいくつか異なる点があり、それぞれに特徴や申請条件があります。
補助金は、政府や自治体が特定の事業活動を支援する目的で提供する資金です。
例えば、「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」のように、設備投資や業務効率化を目的としたものが多くあります。
補助金は申請期間が限られているため、その期間内に利用したい制度に申請する必要があります。
ただし、多くの補助金では採択枠を上回る応募が集まるため、申請したからと言って必ずしも補助金を受給できるとは限りません。
また、補助金の支給は「後払い方式」が一般的で、採択された事業者はまず自費で事業を進め、その後、補助金を受け取る流れとなります。
補助金については下記コラムで詳しく解説しています。
補助金とは?仕訳・会計処理の方法を正しく押さえて資金調達に活用しよう
助成金は、企業の雇用促進や労働環境改善を支援するために提供される資金です。
代表的なものに、「人材確保等支援助成金」や「トライアル雇用助成金」などがあります。
助成金は、基本的に一定の条件を満たせば受給できるため、補助金よりもハードルが低いのが特徴です。
例えば、新たに従業員を雇用し、一定期間継続雇用することで支給されるものなどがあります。
助成金については下記コラムで詳しく解説しています。
助成金とは?補助金との違い?メリットは?活用できる助成金を紹介!
補助金・助成金には多くのメリットがあり、活用することで経営の安定や事業の成長に役立てることができます。
補助金や助成金の最大のメリットは、返済不要であることです。
事業資金を調達する場合は銀行融資などが一般的な資金調達手段となりますが、融資では返済が必要となるため、長期的には経営を圧迫することがあります。
一方、補助金や助成金であれば、経営負担を増やすことなく事業資金等に活用できます。
例えば、新しい設備を導入する際に補助金を活用すれば、自己資金の負担を減らしながら生産性を向上させることができます。
助成金の中には、人材確保や労働環境の改善に役立つものが多くあります。
例えば、人材確保等支援助成金を利用すれば、従業員の採用や研修の費用を支援してもらえます。
これにより、企業は新たな人材を確保しやすくなり、従業員のスキルアップも図ることができます。
労働環境が改善されれば、離職防止につながり、企業が成長するための良いサイクルを築くことができるでしょう。
補助金を活用することで、新しい設備やITシステムの導入がしやすくなります。
例えば、IT導入補助金を利用すれば、業務のデジタル化を進め、業務効率の改善につながり、生産性が向上します。
これにより、経営の安定化や競争力の強化につながります。
補助金や助成金は有用な制度ですが、利用にはいくつかの注意点があります。
まず、補助金助成金は原則「後払い」であるため、事業を実施するには事前に自己資金を準備する必要があります。
また、申請手続きが煩雑で、書類の不備があると不採択となることがあります。
そのため、申請前に専門家(税理士や社労士)に相談することも検討すると良いでしょう。

建設業では、資金繰りの課題や労働環境の変化に対応するために、補助金・助成金の活用がとくに有効です。
2024年4月から、建設業を含む複数の業界にて、それまで猶予されていた時間外労働の上限規制が適用されました。
これにより長時間労働が制限され、より良い働き方の実現が期待できる一方で、これまで時間外労働が常態化していたため不要だった雇用の増加や工期の遅延などが懸念されています。
この問題を、2024年問題と呼びます。
建設業では安定的な経営と健全な労働環境のバランスに注力しなければなりませんが、この課題に対応する手段の一つとして、補助金や助成金を活用できます。
建設業では、2024年問題の他にも2025年問題の影響が指摘されています。
2025年問題とは、75歳以上の後期高齢者が急増することによる諸問題を指します。
建設業においては、この影響により人手不足が加速する懸念があります。
企業によっては、ベテランの建設業従事者が退職することによるノウハウの喪失も問題となるでしょう。
こうした課題に対しても、補助金や助成金の活用が改善の足がかりの一つとなります。
建設業では、工事の完成後に代金を受け取るまでの期間(支払サイト)が長く、ほかの業界と比べて資金繰りが厳しくなりやすい特徴があります。
しかし、補助金を活用することで、一時的な資金負担を軽減することにつながります。
建築資材や人件費の高騰が続いていることも、建設業における大きな課題の一つです。
設備投資や新技術導入の際に補助金を活用することで、コスト負担を抑えながら事業を継続し、経営の安定を図ることができます。

ここからは、建設業でおすすめの5つの補助金についてご紹介します。
なお、補助金の内容や申し込みの条件は年度によって変更があるため、申し込む際は必ず最新の情報を確認してください。
IT導入補助金は、業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策などを目的に、ITツールやシステムの導入を支援する補助金です。
例えば、建設現場での施工管理をITツールで行う場合や、経理・会計業務をデジタル化する際に活用できます。
施工現場での進捗管理や材料発注、スタッフの稼働状況などを一元管理できるソフトウェアを導入することで、作業効率が大幅に向上し、時間的コストや人件費の削減につながります。
ものづくり補助金は、新製品の開発や新技術の導入を支援する補助金です。
建設業では、新しい工法や建設機械の導入に活用できます。
例えば、3Dプリンタやドローンを使って建物の設計図作成や現場調査を効率化する設備投資を行う場合、この補助金を活用することができます。
ただし、申請の際には単なる機器の導入ではなく「新しい技術の活用で生産性を改善すること」を明確に説明する必要があるので、その点には注意が必要です。
小規模事業者持続化補助金は、小規模な企業や事業者を対象に、販路開拓や生産性向上を支援する補助金です。
建設業では、新しい営業活動やマーケティングのために活用できます。
例えば、新たな顧客層をターゲットにした広告活動やウェブサイトの制作、営業ツールの導入費用のために支給してもらえる可能性があります。
事業再構築補助金は、事業転換や新しいビジネスモデルへの転換を支援する補助金です。
例えば、既存の建設業の業態から、環境に配慮した建材を使用するエコ建設業務への転換や、テレワークを取り入れるためのIT設備の導入などが考えられます。
社会情勢の変化に適応するため、既存事業の枠組みを超えて、新たな市場やニーズに対応した事業展開を目指す場合に活用できます。
中小企業省力化投資補助金は、事業の生産性向上を目的に、省力化や自動化設備を導入するための補助金です。
建設業では、例えばロボットを使った施工機械の導入や、AIを活用した現場管理システムの導入に使用できます。
これにより、現場作業の効率が向上し、作業時間の短縮やコスト削減が可能となります。

続いて、建設業におすすめの4つの助成金についてご紹介します。
補助金と同様に、助成金の申し込みを検討する際も最新の情報を必ず確認するようにしましょう。
人材確保等支援助成金は、人手不足解消のために新たな従業員を雇用したり、労働環境を改善したりするために支給される助成金です。
例えば、若手の職人を雇用し、その教育訓練を行う場合に支給されます。
また、長期的に職場への定着を促すために、雇用契約の更新や、再雇用された従業員への支援も行われます。
これにより、労働力の安定的な確保が可能となり、採用にかかるコストを事業投資や設備投資に回すことができます。
トライアル雇用助成金は、未経験者や就業経験が浅いなど安定的な就職が難しいとされる求職者を一定期間試用雇用し、その後、一定条件を満たすことで支給される助成金です。
建設業では、新たな技能を身につけたいと考えている求職者を短期間で試用し、その後正式に雇用契約を結ぶことができます。
これにより、企業は新たな労働力をリスクなく確保でき、求職者も経験を積むことができます。
業務改善助成金は、業務の効率化や生産性向上を目的とした改善を行う企業に対して支給される助成金です。
建設業では、例えば工事現場での安全管理システムの導入や、作業環境を改善するための設備投資に活用できます。
これにより、労働環境の改善や作業効率が向上し、事故の防止や品質の向上にもつながります。
業務改善助成金の助成を受けるには、業務改善と併せて事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げることが条件となります。
働き方改革推進支援助成金は、働き方改革を実施する企業に対して支給される助成金です。
建設業界では、過重労働や長時間労働が課題となっていますが、この助成金を利用して、労働時間の短縮やフレックスタイム制度などを導入することができます。

補助金・助成金は事業の成長や経営の安定のために活用できますが、原則後払いである点を考慮し、別の資金調達手段も検討しておく必要があります。
そこでおすすめなのが、迅速な資金調達が可能な「ファクタリング」です。
ファクタリングは、企業が持つ売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する資金調達手段です。
本来は売掛金の入金までに一定期間待たなければならないところ、ファクタリングの審査に通れば最短即日で現金化されるため、資金繰りの改善に役立ちます。
とくに建設業では、売掛金入金までの支払サイトが長くなりがちのため、ファクタリングが役立つ場面が多くあるでしょう。
ファクタリングの契約方法には、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの2種類があります。
2者間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社の間で契約が行われるため、ファクタリングを利用する際に売掛先に承諾を得る必要はありません。
必要書類を用意し、審査に通過すれば、最短即日で現金化できるのが2者間ファクタリングの特徴です。
一方、3者間ファクタリングでは、利用者、ファクタリング会社とあわせて、売掛先も含めた3者間で契約が行われます。
ファクタリングを利用する際には売掛先の承諾が必要となりますが、2者間ファクタリングと比較して手数料が安めに設定されるのが一般的です。
ファクタリングを利用する際には、手数料の確認が重要です。
2者間ファクタリングの手数料は8%~18%、3者間ファクタリングは2%~9%が相場となっており、ファクタリング会社や売掛金の内容によって手数料が変動します。
できるだけ手数料を下げて利用するには、複数社で相見積りを取るのがおすすめです。
ファクタリングを利用するメリットとして、最短即日で資金調達が可能である点が挙げられます。
一般的な銀行融資では、審査や手続きに数週間~長くて1か月以上の時間がかかりますが、ファクタリングでは売掛金を売却することで資金が必要なタイミングで資金調達が可能となります。
売掛金の未回収リスクを回避できる点も、ファクタリングの大きなメリットです。
ファクタリングでは一般的に、万が一売掛先が倒産した場合も利用者に補償を求めない「償還請求権なし」の契約が行われます。
これにより、ファクタリング契約後は利用者が未回収リスクを負うことがありません。
利用者の信用力や経営状況に関係なく利用できる点も、ファクタリングのメリットの一つです。
ファクタリングの審査では利用者の信用力よりも売掛先の信用力が重視されるため、利用者の経営状況が厳しくても審査にはほとんど影響しません。
建設業の資金繰り改善のポイントについては下記コラムで詳しく解説しています。
売掛金の回収期間が長い?建設業における事情と資金繰り改善のポイント
補助金・助成金は国から支援される返済不要の資金調達手段のため、利用できる制度は積極的に利用していくのがおすすめです。
本記事では建設業におすすめの補助金・助成金についてご紹介しましたが、年によって細かい内容や実施される制度が異なるため、必ず最新の情報を確認し、資金繰りの改善や事業の成長のために役立ててください。
資金繰りを改善し、必要な投資を必要なときに行うための手段としては売掛金を売却するファクタリングもおすすめです。
当機構でも、最短で即日の資金調達が可能なファクタリングサービスをご提供しています。
手数料は1.5%~と業界でも最低水準となっており、売掛金に近い金額での調達が叶います。
AIの導入により素早い手続きを可能にした「FACTOR⁺U」では、申し込みから最短40分での入金も可能となっており、緊急の現金不足にご活用いただけます。
当機構は関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」であるため、中小企業や個人事業の事業主様に対し専門的な支援を行うことが可能です。
資金繰りにお悩みの際は、中長期的な改善についてもご提案が可能なため、ぜひお気軽にご相談ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。