

Same day
Procurement
Diagnostics
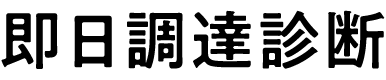
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

ファクタリングの利用を検討する中で、「現金化にあたって消費税はかかるのか」と懸念している方もいるのではないでしょうか。
ファクタリングによる資金調達は国税庁によって定められている「非課税取引」にあたるため、基本的には消費税がかかりません。
ただし、契約の際に「債権譲渡登記」の必要がある場合は一部項目に消費税が課税されるため、どのような場合に課税対象となるのかを知っておくのがおすすめです。
そこで今回は、消費税の概念についてお伝えしながら、ファクタリングが非課税である理由を解説します。
ぜひご覧ください。
【注目】ファクタリングをお急ぎの方へ
ファクタリングは売掛金の売却であり、元となる売掛金にすでに消費税がかかっている状態のため、ファクタリング自体は消費税の課税対象外です。
もし消費税を上乗せしようとするファクタリング会社があれば、悪徳業者の可能性があります。
当機構は、関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」であり、安心してファクタリングサービスをご利用いただけます。
また、請求書と通帳のコピーをアップロードするだけで審査を受けられるAIファクタリング「FACTOR⁺U(ファクトル)」も提供しています。
契約まで全てオンラインで完結しますので、お急ぎの方はぜひお問い合わせください。
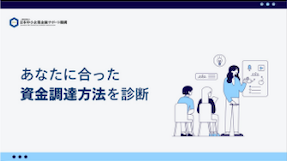
本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金を売却することでスピーディーに資金調達ができる金融サービスのことです。
売掛先から売掛金が支払われる前に売掛金を現金化できるので、資材・機材代の支払いや人件費確保などで今すぐ現金が必要になった場合に役立ちます。
企業や個人事業主としての売上があれば、ほぼ確実に売掛金を保有しているため、不動産担保融資などが利用できない中小企業や個人事業主にも利用しやすい資金調達手段として注目を集めています。
契約方法には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」があり、現金化までのスピードや手数料に違いがあります。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
2者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社間のみで行われる契約のことです。
ファクタリング会社は利用者から必要な申請書類を受け取ると、すぐさま審査に入り、審査を速やかに完了させます。
審査に問題なければ、会社によって差はありますが、当日~3営業日ほどという非常に速いスピードで入金が行われます。
2者間でのやりとりであるため、手続きに手間と時間を要することなく資金調達ができます。
また、契約に売掛先が関与しないので、売掛先との信頼関係を崩すことなく資金調達ができるのも大きなメリットです。
ただし、スピーディーに取引ができる一方で、3者間ファクタリングよりも手数料が高めに設定されています。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社だけでなく売掛先も参加して契約を行います。
利用者が資金調達を希望する際は売掛先の承認を得なければならないため、ファクタリング会社にとっては未回収リスクを軽減できます。
これにより、2者間ファクタリングよりも手数料が安く設定されているのがポイントです。
ただし3者間ファクタリングでは、売掛先にファクタリング利用の承諾を得た上で契約を結ぶため「資金繰りが苦しいのではないか」といった印象を売掛先に与えてしまうこともあります。
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
ファクタリングを利用することで、以下のようなメリットが得られます。
2者間ファクタリングの項目で解説したように、ファクタリングでは審査が問題なく進めば最短即日という早さで口座への入金が行われます。
この早さは、その他の資金調達と比べると圧倒的に早く、例えば融資では種類にもよりますが数週間以上は必要となるケースが多いです。
なお、3者間ファクタリングでは売掛先の承諾を得た上でファクタリングの手続きが進められることから、2者間ファクタリングに比べると入金までのスピードが遅めです。
それでも、必要な金額を短期間で調達できることは企業の資金繰りにとって大きなメリットとなります。
掛取引では、売上が確定してから実際に代金が支払われるまで、一定の期間を必要とします。
一般的には30日~60日程度で、業界の商慣行によってはもっと長いこともあります。
仮にこの期間に売掛先が倒産した場合、納入企業からしたら商品・サービスは提供したのに代金は支払われない「未回収の売掛金」が発生します。
しかし、ファクタリングの契約が締結されている場合、仮に売掛先が倒産して貸し倒れが発生しても、貸し倒れのリスクはファクタリング会社が負います。
そのため、利用者がすでに受け取った現金をファクタリング会社へ支払う必要はありません。
利用者が返却する必要がないのは、ファクタリングが原則として「償還請求権なし(ノンリコース)」の契約となるためです。
償還請求権とは、このケースでいえば、譲渡された売掛債権に問題があった場合、譲渡元までさかのぼって損害分を請求できる権利を指します。
仮に償還請求権があった場合は、売掛先が倒産すると貸し倒れにて支払われなかった分を利用者が補填しなければなりませんが、ファクタリングではこの心配がありません。
なお、売掛先の経営状況が極端に悪い場合は、ファクタリングの審査に通らないことがあります。
その場合、自社の売掛金の未回収リスクが高まるため、該当する売掛先との取引を縮小し、新たなクライアントを増やすなどのリスク対策が必要になるでしょう。
償還請求権については下記コラムで詳しく解説しています。
償還請求権とは?ファクタリングに重要なリスクや注意点を解説
資金調達における審査では、大きくいえば「支払能力」が問われます。
例えば融資では、利用者が後に支払いしなければならないため、利用者の支払能力が審査の対象となります。
ファクタリングにおいては、売掛金の代金を支払う義務を負っているのは売掛先のため、審査は主に売掛先の支払能力が対象となります。
そのため、自社が現在赤字状態かどうかは、ファクタリングの審査にそれほど影響しません。
税金を滞納しているなど、非常に経営状況が悪い状態であっても、その改善姿勢が見られないなどの極端な場合を除いてファクタリングは問題なく利用できます。

冒頭でもお伝えしましたが、ファクタリングは国税庁によって定められている「非課税取引」にあたることから、消費税はかかりません。
売掛金の売買時に発生する資金だけでなく、ファクタリング会社に支払う手数料も含めて非課税となります。
では、そもそも消費税はどのような場合に発生しているのでしょうか。
また、国税庁が定める「非課税取引」とは一体どんな内容なのでしょうか。
消費税とは、商品やサービスなどの利用に対して公平に課税される税金のことです。
納税者は消費者側ですが実際に税金を納めているのは事業者側であることから、納税者が異なる「間接税」とも捉えられます。
商品やサービスなどを提供する事業者は、商品やサービスの価格を設定する際に税額分を上乗せしているので、消費者は税額を含めた代金を支払うことになります。
事業者は消費者が支払った税金をいったん預かる形になり、納税のタイミングで消費者から徴収した税金を納めます。
つまり、日本の消費税は消費者の代わりに税金を納める「代理納付」という形を取っているのです。
消費税は日本国内において、対価を得て行った取引や資産の譲渡などにかかるものですが、一方で消費税が課税されない「非課税取引」「免税取引」「不課税取引」も存在します。
参照:消費税の仕組み|国税庁
消費税が課税される条件としては、国税庁により以下のように定められています。
消費税が課税されるのは、日本国内にて行われる取引に限られます。
納税の仕組みは国によって変わるため、これは当然といえるでしょう。
国外に向けて行われる商品・サービスの提供では、消費税は免税されます。
消費税の免税の対象となるには、商品・サービスを提供する対象が国外にあることが条件ですが、一部免税にならないケースもあります。
例えば、日本国外に居住している個人であっても、日本国内において利益を得られる場合は消費税の対象となります。
また、日本国外に本社を持つ法人でも、日本国内にある支店や営業所が対象であればやはり消費税の対象となります。
事業者が事業として行う取引に対し、消費税が課税されます。
ここでいう事業者とは、法人および個人事業主を指します。
法人はそもそも、事業を行う目的で設立される組織であることから、法人が行う取引は原則として全て消費税の課税対象となります。
また、ここでいう「事業として」とは、対価を得て行う資産の譲渡等を繰り返して行うものを指します。
例えば、個人事業主が自家用車の売却を行った場合は、繰り返して行う取引とはいえないため事業として認められません。
一方、中古車販売店が中古車の売却を行う場合は、事業として認められます。
また、法人が事業において使用していた社有車(トラックや営業車など)を売却した場合は、事業に関連する取引とみなされるため、これも事業として認められ消費税の課税対象となります。
さらに、個人事業主でも、個人で行う配送業や介護タクシーなどに使用していた車両を売却する場合は、事業として認められ、課税の対象になります。
消費税が課税されるのは、上記のケースに合わせて、さらに対価を得て行われる取引が対象となります。
無償で行われる取引や、寄付、補助金、賞金などについては対価が発生するとは認められないため、課税対象ではありません。
消費税は、資産の譲渡等において課税されます。
ここでいう譲渡等とは、資産(有形・無形)の販売、資産の貸し付け、サービスの提供を指します。
特定仕入れとは、国税庁では「事業として他の者から受けた「特定資産の譲渡等」」と説明しています。
特定仕入れに該当する身近な例として、国外から日本国内の事業者へ提供される多くのインターネットサービス(クラウドサービス、広告配信、予約システムなど)や、国内のテレビ・映画などへの国外からの出演、コンサートへの出演、大会への出場などを指します。
このケースでは、国内にいる人は商品・サービスの提供側ではなく、代金を支払う側です。
消費税は日本国の法律では代金を徴収する側が国に納めますが、この特定仕入れのケースでは反対に代金を支払う側が納税を行います。
このように消費者側が納税を担う形をリバースチャージ方式と呼びます。
特定仕入において、リバースチャージ方式が取られている理由は2つあります。
インターネットサービスは、かつては免税対象でしたが、国外のサービスも増えてきた中、国内のサービス事業者にとって不利な状況であることから同等の消費税がリバースチャージにて徴収されることになりました。
また、国外から国内のテレビ・映画の出演依頼などは、かつては通常の消費税と同様に提供側(国外の事業者)から徴収していましたが、確実な徴収が困難なことからリバースチャージ方式への変更となりました。
外貨貨物の引取りとは、言い換えれば輸入取引のことであり、国外から船舶や航空機で物品を輸入したとき、消費税が課税されます。
国外から貨物を輸入するとき、港あるいは空港に到着すると、いったん保税地域に保管されます。
このときに輸入申告を行い、必要な関税と消費税を支払った上で貨物を引き取ります。
反対に、消費税が課税されない取引もあります。
これにはいくつか種類があるので、以下にてご紹介します。
不課税取引とは、簡単にいえば、上記にてご紹介した消費税の課税対象とはならない取引を指します。
つまり、国外との取引や対価を得て行うことではない寄付や贈与、そのほか出資に対する配当などが該当します。
上記にてご紹介した消費税の課税対象ではあるものの、社会意義的に課税がそぐわないものは課税対象から外れ、非課税取引となります。
土地や有価証券などの譲渡、貸し付けなどの利子、社会保険医療などが該当します。
免税とは、簡単にいえば、国外に対して商品の譲渡を行う輸出と、国外に対してサービス提供を行う輸出類似取引に対して、消費税を払わなくても良いとするものです。
上記「国内で行われる取引」にてすでに登場している解説になりますが、国外向けに行われる取引は、消費が国外にて行われるとみなされ、消費税が免除されます。
身近なところでは、空港などで利用できる免税店が想像されます。
免税店では、国内にて消費を行うものの、消費者が実際にその対価を享受できるのは国外に出た後のことであるため、輸出と同質であると扱われ消費税が免除されます。
ファクタリングは「事業として行われる無形資産の譲渡」であるため、課税対象にも思えますが、ここまでで紹介した中では社会意義的にそぐわないため課税しないとされる「非課税取引」に該当します。
ファクタリングで発生する債権の取引は「有価証券の譲渡」と同義であると、国税庁によって定められているからです。
また、資金調達の際にかかる手数料も非課税とみなされており、これは国税庁が定める「預金や貸し付け金の利子など」の項目に記載されています。

ファクタリングの基本的な取引は非課税ですが、「債権譲渡登記」が必要な場合は消費税の課税対象となります。
債権譲渡登記とは、ファクタリング会社が売掛債権を譲り受けたことを第三者に対抗するために必要な要件の一つです。
ファクタリング会社は譲渡された債権を確実に回収できるかどうかを重視しているので、譲渡された債権が実は他の会社にも譲渡されていた(二重譲渡)という事態を防がなければなりません。
3者間ファクタリング契約であれば、契約段階で売掛先の承認を得る必要があるので、二重譲渡のリスクが少なく債権譲渡登記を行う必要がありません。
ところが2者間ファクタリング契約の場合は、利用者とファクタリング会社間のみで取引が行われるため、ファクタリング会社からみるとこっそりと二重譲渡が行われるリスクが高くなります。
そのため、「この売掛金は自社の債権である」という事実を証明できる債権譲渡登記を取り入れ、二重譲渡を防止するのです。
債権譲渡登記の際にかかる登録免許税や印紙代は非課税ですが、登記手続きを依頼する司法書士に支払う報酬や交通費などの実費相当額は消費税の課税対象となります。
2者間ファクタリングにおいては債権譲渡登記を行うことを条件としているファクタリング会社もあるので、消費税を支払う義務が発生することも視野に入れておきましょう。
ファクタリング会社の中には、利用者に金融知識がないのを良いことに見積書や請求書に消費税を記載し、堂々と請求してくる悪徳業者が存在します。
優良なファクタリング会社であれば、本来不要であるはずの消費税を請求してくることはまずありません。
したがって消費税を請求するファクタリング会社は悪徳業者である可能性が非常に高く、契約してしまうと法外な費用を求められたり自社に不利な取引に持ち込まれてしまったりするリスクがあります。
もしも契約前の段階で消費税を請求された場合は早急にやりとりを打ち切り、契約をしないように注意しましょう。
悪徳なファクタリング業者については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングは違法ではない!その根拠と悪徳業者・優良業者それぞれの特徴を解説
ファクタリングは国税庁が定める「非課税取引」に該当するため、売掛金の売買取引はもちろん、ファクタリング会社に支払う手数料にも消費税はかかりません。
ただし、2者間ファクタリングで契約する際に「債権譲渡登記」が必要となった場合は、司法書士への報酬や交通費などの実費相当額に対して消費税が課せられるので注意しましょう。
もしも契約を進める段階で見積書や請求書に消費税の記載があった場合、そのファクタリング会社は悪徳業者である可能性が非常に高くなっています。
契約に進む前に契約書や見積書の内容をしっかりと確認し、不要な課税項目がないかどうかをしっかりと確認するように心掛けましょう。
当機構では、ファクタリングのご相談受付から契約までのサポートを行っています。
経験豊富な専任スタッフがあらゆる観点からお客さまのニーズに合った最適な方法をご紹介いたします。
「ファクタリングについて相談したい」という方は、この機会にぜひお問い合わせください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。