

Same day
Procurement
Diagnostics
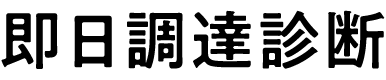
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

個人事業主でも事業継続や拡大のために、現金が必要になる場合は出てきます。
そのような場合には、個人事業主でも融資で運転資金を調達することが可能です。
そこで今回は、個人事業主が融資を受けられる条件や、利用できる融資の種類、そのほかの資金調達方法についてご紹介します。
資金調達については下記コラムでも詳しく解説しています。
資金調達とは?代表的な11の方法とメリット・デメリット
【注目】急ぎで資金調達したい個人事業主の方へ
個人事業主でも融資を受けることは可能ですが、審査にはある程度の時間がかかり即日での資金調達は難しいでしょう。
早急に資金調達したい方には、ファクタリングをおすすめいたします。
お持ちの売掛金をファクタリング会社に売却することで即日現金化が可能です。
当機構のファクタリングなら申し込みから契約までオンラインで完結し、振り込みまでの時間は最短3時間です。
17時までに契約が完了すれば即日振込が可能なので、この機会にぜひ当機構にご相談ください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

個人事業主でも銀行などの融資制度を利用して運転資金を調達することは可能です。
ただし、個人事業主が融資を受けるには「開業届を提出する」「確定申告をしている」の2つの条件をクリアする必要があります。
個人事業主が融資を受けるには、開業届を提出している必要があります。
開業届とは、事業を開始する際に税務署へ提出する書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
事業を開始してから1か月以内の提出が推奨されています。
なお、提出がなくてもペナルティはないため、開業届を提出せずとも事業を行うことは可能です。
ただし確定申告を青色申告で行う場合は、開業届を提出していることが必須になります。
融資を受ける場合は開業届が必須というわけではありませんが、提出しているとスムーズに進むケースが多いといえます。
個人事業主は、事業で得た所得に対する所得税を支払うために確定申告を行う必要があります。
源泉徴収などで追加納税の必要がない場合は確定申告をしなくても良いケースもありますが、融資を受けたいと考えている場合はどのケースでも確定申告を行っておくのが良いでしょう。
融資を受けるには、自身が事業においてきちんと利益を出し、返済能力があることが問われます。
銀行など融資を行う機関は確定申告書類や決算書などを見て信用の判断を行うため、客観的に数字を照明できる確定申告は必須といえます。
確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の事業などにおける所得を計算し、原則として翌年の3月15日までに行います。
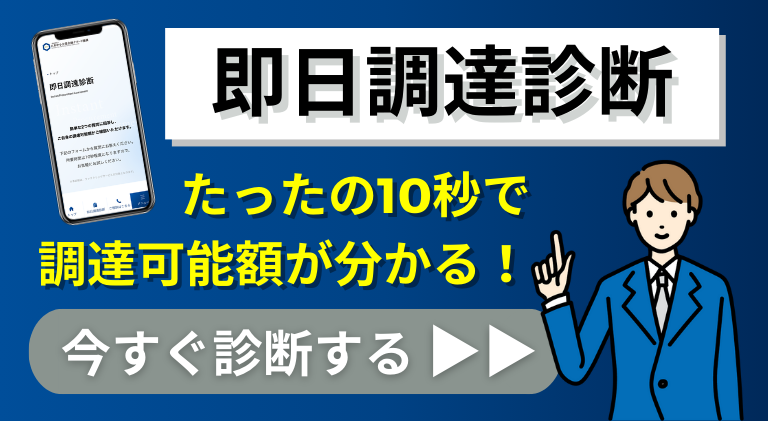

ここからは、個人事業主が利用できる具体的な融資制度を6つご紹介します。
個人事業主が融資を求める際、まず検討できるのが日本政策金融公庫の融資です。
日本政策金融公庫は政府系金融機関の一つで、国民生活・中小企業・農林水産の3つの事業を展開し、事業者の支援を行っています。
日本政策金融公庫では個人事業主でも受けられる融資制度も用意しています。
個人事業主のほとんどが対象となる「一般貸付」、売上の減少をカバーしたい際に申請する「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」、外的要因により緊急的に現金が必要なときに受けられる融資などが存在します。
日本政策金融公庫は、政府による公庫であるために申請のハードルが低く、例えば銀行に比べて金利が低い点がメリットです。
融資によっては、保証人を付けずに貸し付けを得られるものもあります。
返済期間が5年以上からと長い点も特徴で、月々の負担を減らすことができます。
一方で、融資にかかる審査は銀行に比べて厳しい傾向にあり、申請から融資開始までの期間もある程度の長さを見込んでおく必要があります。
自己資金のチェックなどもあるため、どのような融資があるかを把握しておき、計画的に利用できるようにするのがおすすめです。
融資を行う機関としてまず思い浮かぶのは銀行かもしれませんが、個人事業主、ひいては中小企業の場合は信用金庫や信用組合のほうを先に検討しましょう。
銀行は主に大企業を相手に融資を行いますが、信用金庫・信用組合は地域の個人事業主や中小企業を相手に融資を行っているためです。
一般社団法人全国信用金庫協会は、信用金庫のことを「地域の方々が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関」と説明しています。
信用金庫は会員から現金を預かり、地域の反映、すなわち地域の個人事業主や中小企業への支援などを行います。
信用金庫は非営利法人であることも特徴であり、営利法人である銀行との違いにもつながっています。
信用金庫・信用組合で融資を受ける場合、日本政策金融公庫よりは金利が高くなる傾向にありますが、地域独自の制度があるかもしれないため優先的に確認するのが良いでしょう。
銀行が主に相手としているのが大企業とはいえ、個人事業主も銀行の融資を利用することができます。
融資窓口か、行員に付き合いのある人がいればその人経由で融資の相談を行うことになります。
銀行から融資を受ける場合は、決算書をはじめとした書類を提出し厳格な審査を受けます。
その後銀行内での格付けが行われ、融資を行って良いかどうか、融資額はいくらかなどが決定されます。
銀行や信用組合から融資を受ける際、これらの金融機関がリスクを負う形になる場合は金融機関が直接審査を行う「プロパー融資」となります。
この審査は厳しいものですが、信用保証協会からの保証を得られている場合であれば、「信用保証付き融資」を受けられるようになります。
保証を得るには、例えば先に「制度融資(自治体・信用保証協会・指定金融機関が協調して行う融資制度)」を利用し、確実な返済を行うことが挙げられます。
こうした信用があれば、プロパー融資の審査も通りやすくなっていくでしょう。
なお、個人事業主が展開する事業規模であれば、日本政策金融公庫から受けられる融資で十分であることがほとんどです。
さらなる事業拡大を図りたい場合などに、信用金庫や銀行からの融資を検討すると良いでしょう。
地方自治体は、それぞれの自治体の発展や課題解決のために独自の融資制度を用意していることがあります。
条件に合えば低金利で融資を受けられる可能性があるため、都道府県や市町村のWebサイトをチェックしたり、窓口で相談してみたりすると良いでしょう。
なお、自治体では融資のほかに補助金・助成金の制度を実施していることもあります。
補助金・助成金は融資と異なり返済の必要がないため、融資を検討する前に確認するのがおすすめです。
ただし、補助金・助成金を受けるにはその目的と自身の事業がマッチしている必要があります。
銀行やノンバンクなど多くの金融機関で利用できるのが、カードローンです。
カードローンは無担保・保証人なしで申請できる、融資までが早い、原則として使い道に制限がないという特徴があり、早く現金を調達したい場合に適しています。
一方、ほかの融資と比べ金利は高く設定されているため、きちんと返済できるかを考える必要があります。
また、事業者向けクレジットカード(ビジネスカード)を利用する方法もあります。
事業者向けクレジットカードではキャッシング枠から現金を得られるほか、必要な機材などをショッピング枠で購入することもできます。
これらの支払いを分割で返済することも可能ですが、分割払いやキャッシングには比較的高い金利が設定されているため利用の際は注意が必要です。
個人事業主向けとしてはあまり推奨できませんが、ノンバンクから融資を受けることもできます。
ノンバンクとは、預金業務を行わない金融機関をまとめて呼称したもので、広くいえば銀行以外の金融機関を指します。
上記のカードローンなども、ノンバンクで利用する場合はこちらに該当します。
銀行よりは審査が厳しくなく、計画的に借り入れをすることで返済も十分に行えますが、個人事業主の場合はそのほかの融資でまかなうことを考えるのがおすすめです。

資金繰りが厳しくなったときや、事業を円滑に回すために融資を検討する個人事業主は少なくありません。
しかし、安易な借り入れは返済負担を大きくし、経営を圧迫するリスクもあります。
ここでは、融資で運転資金を調達する際に押さえておきたい注意点を紹介します。
個人事業主が融資で運転資金を調達する際は、使い道を明確にしておくことが重要です。
現金の使い道が曖昧だと、金融機関からの信頼を得にくく、審査で不利になる可能性があります。
また、目的がはっきりしていないと、適切な額の借り入れができず、資金繰りがかえって悪化する恐れもあります。
例えば、仕入資金、人件費、設備の維持費など、具体的にどの費用にいくら必要なのかを整理しておくと、計画的な借り入れと返済がしやすくなります。
運転資金を融資で調達する際は、借入額が適正かどうかをしっかり確認しましょう。
必要以上に借りてしまうと利息負担が増え、返済が経営を圧迫する恐れがあります。
一方で、少なすぎると資金繰りが改善せず、再び追加の融資が必要になります。
仕入れや人件費、家賃などの経費を具体的に見積り、どれだけの現金が必要なのかを明確にしておくことが大切です。
融資を受ける際は、利息や各種手数料を事前に確認しておくことが欠かせません。
利率がわずかに違うだけでも、返済総額に大きな差が生じることがあります。
また、融資実行時の事務手数料や保証料、繰上返済時の手数料など、見落としやすい費用も含めて把握しておく必要があります。
とくに短期間での借り入れでは、手数料の割合が高くなるケースもあるため注意が必要です。
複数の金融機関を比較し、総支払額ができるだけ少なく済む条件を選ぶことで、返済負担を抑えることができます。
融資を受ける際には、無理のない返済計画を立てることが非常に重要です。
借入額や金利、返済期間をもとに、毎月どれだけの返済が発生するのかを具体的にシミュレーションしましょう。
売上の見込みや支出とのバランスを考慮せずに借り入れを行うと返済が滞り、信用を損なうリスクがあります。
とくに個人事業主は、事業と生活の資金が密接に関係するため、返済負担が日常の経営に大きな影響を与える可能性があります。
返済に充てる余力があるかどうかを冷静に見極め、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。

上記でご紹介した融資制度を利用したいと考えたとき、個人事業主は以下にご紹介するポイントを押さえておきましょう。
クレジットカードやカードローンを用いた資金調達を除き、融資には審査が要るため申請から融資開始まで一定の期間が空きます。
そのため、各融資制度に必要な書類を調べておき、計画的に準備を進めることが重要です。
必要な書類としては、例えば開業届、事業計画書、確定申告書、決算書、資金繰り計画表などがあります。
中でも重要な書類の一つが、将来どのような事業を行うのかを説明する事業計画書です。
運転資金を調達する際には、人だけでなく事業に対しても審査が行われるため、どの融資を受けるにしても、その事業によって得られる利益や将来性が重視されます。
融資を検討する際は、できるだけ自己資金を用意しておくのがおすすめです。
自己資金があるほうが融資額を少なくできるという点以外に、審査に通りやすくなるというメリットがあります。
融資時に必要な自己資金はどの融資を受けるかによって変わりますが、必要額の1割~3割は確保しておくのが良いでしょう。
5割まで確保できると、多くの融資において審査が有利になります。
なお、自己資金が全くないと審査に通らなくなるわけではなく、総合的に融資に値すると判断されれば借り入れ可能です。
融資は、可能であれば開業前に受けるのがおすすめです。
開業前であれば事業がまだ始まっていないため、自己資金や事業計画書の妥当性で判断するので、審査に通りやすくなります。
しかし、開業後に融資を受けるとなると、資金ショートなど業績悪化で申請するケースが多くなり、その点を厳しく審査されるため、資金調達が難しくなります。

ここまで個人事業主が利用できる融資制度についてご紹介してきましたが、運転資金を調達する方法には以下のようなものもあるため、こちらも確認してみてください。
それぞれの自治体が実施している助成金・補助金の制度は、融資と違って返済の必要がなく、運転資金の調達先として活用できます。
中小企業や個人事業主を対象とした助成金・補助金を実施していることも多いため、自身の自治体の情報を確認しましょう。
なお、助成金は自治体の掲げる要件に合致していれば申請によりほとんどは受給可能ですが、補助金は上限が決まっていることがほとんどで、審査の上でより相応しいと判断された事業者へ受給されるという違いがあります。
一方で、実施する自治体の中でもこれらの区別が曖昧になっていることもあるため、要件を細かく確認することが大切です。
助成金・補助金については下記コラムで詳しく解説しています。
助成金と補助金の違いをわかりやすく解説!管轄・予算・給付額・期間の相違点とは
クラウドファンディングを実施し、エンドユーザーから直接支援をしてもらう選択肢もあります。
クラウドファンディングとは、インターネット上の該当サイトにてユーザーへ商品やサービスをアピールし、その開発や準備資金を支援してもらうというものです。
現金を必ず集められるとは限りませんが、魅力をうまくアピールできれば十分な現金を短期間で集められる可能性があります。
クラウドファンディングについては下記コラムで詳しく解説しています。
クラウドファンディングとは?メリットやデメリットは?成功事例などをご紹介
契約している生命保険の解約を行うことで運転資金を調達するという方法もあります。
この方法は払戻金のある保険に加入している場合に可能で、十分な期間加入していた場合、まとまった額の払戻金を短期間で受け取れます。
また、法人契約の保険の場合、払戻金は利益として計上されるため、現金が増えることによりその期の利益額を減らしたくない場合にも有用です。
一方で、ほかの保険への加入がなければ無保証の状態になってしまう、再度同じ保険に加入できるとは限らない、利益形状により所得が上がって法人税率が一段上がってしまう可能性がある、といったデメリットもあるため、慎重に検討しましょう。
とくに開業前の運転資金を調達する手段として、家族から資金提供を受けることは珍しくはないものです。
堅苦しい審査などを必要としない点で、人によっては気軽にできる資金調達といえます。
現金を借用する場合は、家族とはいえど借用書を作成するのがおすすめです。
きちんと約束した返済までの計画がなければ、贈与扱いとみなされ、現金の額によっては贈与税の納税が発生する可能性があります。
また、口約束ではなく書面で約束を取り交わすことで、家族間の無用な争いを避けるという役割もあります。

個人事業主が資金繰りに悩んだとき、銀行融資以外の選択肢として注目されているのが「ファクタリング」です。
売掛金を早期に現金化できるファクタリングは、審査スピードが速く、原則担保や保証人も不要なため、急な資金ニーズにも対応しやすいのが特長です。
ここでは、ファクタリングの基本的な仕組みや、利用する際のメリット・デメリットについてご紹介します。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
ファクタリングの契約方法には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。
2者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の間だけで契約を結ぶ形態です。
ファクタリングの利用にあたり売掛先からの承諾は不要なため、スピーディーに資金調達ができます。
2者間ファクタリングでは、本来の支払期日が到来したら利用者が売掛先から売掛金を回収し、速やかにファクタリング会社へ送金します。
3者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社に加えて、売掛先も契約に加わる形態です。
3者間ファクタリングを利用する際は、2者間ファクタリングと異なり、売掛先からファクタリング利用の承諾を得る必要があります。
しかし、売掛金の存在をファクタリング会社が売掛先に直接確認できるため、売掛金の未回収リスクが低くなり、3者間ファクタリングは2者間ファクタリングに比べて手数料が低くなる傾向があります。
3者間ファクタリングでは、本来の支払期日が到来したら売掛先がファクタリング会社へ送金します。
2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説
3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!
ファクタリングを利用するメリットは以下の通りです。
ファクタリングのメリットの一つは、売掛金を最短即日で現金化できる点です。
通常、売掛金は請求書に記載されている支払期日まで待たなければ現金化できませんが、ファクタリングを利用すれば、その前に現金を得ることが可能になります。
とくに2者間ファクタリングでは、売掛先の承諾が不要なため、申し込みから現金の振り込みまでが非常にスピーディーに行われます。
急な支払いへの対応や、資金繰りの悪化を避けたい場面でもファクタリングは有効な手段といえるでしょう。
ファクタリングは、銀行融資と比較して審査が柔軟な傾向にあります。
融資の審査では申込者の信用情報や事業の業績などが重視されますが、ファクタリングの審査では売掛先の信用力が主な審査対象となるため、開業間もない個人事業主や赤字決算の場合でも利用できる可能性があります。
ファクタリングを利用するメリットに、売掛金の未回収リスクを軽減できることが挙げられます。
ファクタリングの契約では、基本的に償還請求権がないノンリコース契約を締結します。
そのためファクタリング契約後に万が一売掛先が倒産などの理由で売掛金を支払えない状態になっても、利用者がファクタリング会社から費用を請求されることはありません。
ファクタリングは貸し倒れのリスクも抑えることが可能です。
ファクタリングは「売掛金の売却」という取引であるため、借り入れと異なり利用しても信用情報に記録されることはありません。
そのため、将来的に融資を受ける予定がある個人事業主でも、利用しやすい資金調達方法となっています。
ファクタリングを利用するデメリットは以下の通りです。
ファクタリングの審査において売掛先の経営状態が重視される点はデメリットにもなりえます。
ファクタリング会社は、売掛金が確実に支払われるかどうかを判断するために、売掛先の信用状況や経営状態を中心に審査します。
そのため、利用者自身の経営状態が良好であっても、売掛先に経営不安がある場合は審査に通らないケースもあります。
ファクタリングは売掛金を現金化する手段であるため、基本的に調達できる金額は売掛金の額面までとなります。
例えば100万円の売掛金を保有していた場合、調達できる現金はその範囲内に限られ、手数料を差し引いた分しか実際に受け取れません。
そのため、大型投資や予想以上の資金不足にお悩みの方は、ファクタリングと併せてほかの資金調達方法を検討する必要があります。
ファクタリングを利用する際には、売掛金の額に応じた手数料が発生する点に注意が必要です。
手数料は契約形態によって異なり、2者間ファクタリングでは一般的に8%〜18%、3者間ファクタリングでは2%〜9%が相場とされています。
ファクタリングで資金調達する際は、手数料を差し引いた金額しか受け取れないため、実際の資金調達額が想定より少なくなることもあります。
ファクタリングの手数料については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリング手数料はいくら?相場や内訳、費用を抑える方法を紹介!

ここまで、個人事業主が融資などで資金調達を行うための情報をご紹介してきました。
自身に合った融資制度はどれかについて相談したい場合は、ぜひ日本中小企業金融サポート機構へご相談ください。
当機構では即日ファクタリングサービスを提供しており、個人事業主も対象です。
2者間取引・3者間取引の両方に対応しており、売掛金の買取可能額における下限・上限はないため、効率の良い資金調達が可能です。
手数料は1.5%~で、審査結果は最短30分で提示することも可能なため、即日入金を希望する場合も対応できる可能性があります。
また、当機構ではオンラインファクタリングサービス「FACTOR⁺U」もご提供しています。
審査完了までは最短10分、現金の振り込みまでは申し込みから最短40分で完了するため、急な資金ニーズにも対応可能です。
運転資金の調達を検討中の個人事業主様は、ぜひこの機会にご利用ください。
資金調達は企業だけのものではなく、個人事業主でもしっかり準備をして申請することでさまざまな融資制度を活用することが可能です。
融資以外でも、助成金・補助金の利用やファクタリングなど資金調達をする手段は豊富にあるため、それぞれの方法についてよく調べ、自身の事業に合うものを選択しましょう。
なお、当機構のファクタリングについて詳しく知りたい方、質問やご相談がある方は、ぜひお気軽にお問合せください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。