

Same day
Procurement
Diagnostics
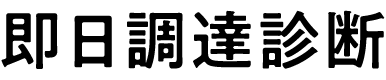
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

売掛先から売掛金の入金がない場合は、そのまま放置してはいけません。
売掛金には時効があり、2020年の民法改正後からは5年と定められています。
5年を過ぎた売掛金は入金してもらえなくなってしまうため、早めに入金してもらうことが大切です。
そこで今回は売掛金の時効をはじめ、時効に余裕がある場合と時効が迫っている場合の対処法をご紹介します。
また、請求書が未送付だった場合の対処法や売掛金が未回収となる前に打てる手段についてもまとめているので、ぜひご参考にしてください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

売掛金の時効は、2020年民法改正施行により「5年」と定められています。
2023年11月に商品を納品し、その代金が翌月末払いだった場合、売掛金の支払い期限は2023年12月31日となります。
しかし、売掛先から売掛金が支払われずそれを放置し続けた場合、2028年12月31日に時効が完成してしまいます。
2020年の民法改正前は債権の時効が原則「10年」と定められていましたが、債権の種類によって短期の時効が定められており、主に短期の時効が適用されていました。
具体的には以下の通りです。
| 時効期間 | 債権の種類 |
| 1年 | 運送料金、飲食代金、宿泊料金、レンタル料金 など |
| 2年 | 商品代金、生産者・小売店などの売掛金 など |
| 3年 | 治療費、自動車の修理費、建築代金、工事代金 など |
| 5年 | マンションの管理費、家賃 など |
上記のように債権の種類によって時効が異なるため、「どれに該当するのかわかりづらい」という問題が起こりました。その問題を解消するため、2020年民法改正施行により売掛金の時効が5年で統一されたのです。
なお、民法改正前の売掛金の短期時効は2年なので、2023年11月現在は2020年3月以前に発生した売掛金の時効が完成しています。
民法改正後は短期時効がなくなり、以下のように統一されるようになりました。
・売掛先が支払期日の到来を知った日から5年
・自社が代金を請求できる日(支払期日)から10年
上記の2つのうち、どちらか早いほうが到達したときに時効が完成します。
とはいえ、売掛先が支払期日を把握していないことはほとんど考えられないため、時効は普通5年となります。
時効の開始期間を計算する際は、「初日不算入の原則」によって支払期限の翌日からカウントを開始します。
そのため、支払期限が2023年12月31日の場合は、時効期間は2024年1月1日からカウントします。時効が完成するのは、2028年12月31日です。
2020年3月以前の取引については、前述したように短期時効が2年なので、2023年11月現在は時効が完成しています。
日本では、新しく法令が制定された際、改正前の出来事には適用されない「法の不遡及」という原則が定められています。
そのため、2020年3月以前の取引に改正後の内容が適用されることはありません。

売掛先に請求書を送ったのにもかかわらず売掛金の入金が遅れており、時効に余裕がある場合は以下の方法で対応しましょう。
まずは売掛先企業の担当者に連絡しましょう。連絡をする際、売掛先を責めてしまうと今後の関係に影響を及ぼす可能性があるため、入金が遅れている旨を伝えるだけに留めておくのが無難です。
請求書の紛失によって入金が遅れている場合は、請求書の再発行を行いましょう。
売掛先が電話に出ない、メールを送っても返信がない、再発行した請求書を送付しても入金してくれないなどの場合は、内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便は、「いつ・誰に・どのような内容の文章を発送したか」を残すことができます。
内容証明郵便を送ると売掛先に売掛金の入金を催促した記録を残すことができるため、訴訟を起こす場合は有力な証拠にもなります。
内容証明郵便を送っても売掛金が入金されない場合は、支払督促の申請を行いましょう。
支払督促は裁判所を利用するため、売掛先の財産の差し押さえができるほどの強い力があります。
売掛先に与えるプレッシャーにより、売掛金の入金に応じてくれる可能性があるでしょう。
支払督促の一般的な申請方法は、まず支払督促申立書を簡易裁判所に提出します。
次に、裁判所から売掛先に支払督促が送られます。このとき、売掛先が異議を出した場合は訴訟に移行します。
支払督促が送達されて2週間以内に異議が出ない場合は、仮執行宣言を求めることができます。
仮執行宣言の申立ては、支払督促が送達されて2週間を超えてから30日以内に行わなければなりません。
仮執行宣言付支払督促の送達が行われたのち、強制執行が可能になります。

売掛先から売掛金が入金されず時効が迫っている場合は、以下の方法で対応しましょう。
時効の完成を防ぐためには、更新または完成を猶予する必要があります。
民法改正前は「時効の中断」「時効の停止」と呼ばれていましたが、民法改正により言葉も変更になりました。
現在は、「時効の更新」「時効の完成猶予」と呼ばれています。
時効の更新は、進行していた時効期間をリセットすることです。
そのため、時効が完成する前に更新をすれば、これまで経過していた期間をなかったことにすることができます。
時効の完成猶予は、時効の進行を一時的にストップさせることです。
時効が完成する前に完成猶予事由が発生した場合、時効の完成を阻止することができます。
ただし、一時的に時効が完成しないことを意味するため、時効期間をリセットできるわけではありません。
では、何をすれば時効を更新・停止できるのか以下にて詳しくご紹介します。
民法改正後、権利についての協議を行う旨の書面による合意があれば、以下のいずれか早いときまでの間は時効が完成しないよう認められました。
・合意があったときから1年が経過したとき
・書面による合意において当事者が協議を行う期間(1年未満)を定めた場合は、その期間を経過したとき
・当事者のどちらか一方から相手方に対し、協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた場合は、その通知のときから6か月を経過したとき
売掛金の時効が迫っているときは、権利についての協議を行う旨の合意を書面で行うと良いでしょう。
時効を延ばすため、売掛金の一部を弁済してもらうのも一案です。
売掛金の一部を弁済してもらうことは、売掛先が売掛金の債務を認めたことになります。
これにより、時効を更新することができるのです。
売掛金債務を承認してもらうと、売掛金の一部を弁済してもらえない場合でも時効を更新することができます。
ただし、口頭だけでのやり取りだとあとからトラブルになる可能性があります。
そのため、売掛金の債務を認めてもらうためにも、売掛先に「債務残高確認書」などを作成してもらうと良いでしょう。
時効が迫っているときは、内容証明郵便による「催告」を行うのも一案です。
内容証明郵便を送ると、時効の進行を6か月間延ばすことができます。
そのため、「時効が完成するまで残り1か月しかないのに、訴訟の準備に1か月以上かかる」という場合は、内容証明郵便を送ると良いでしょう。
ただし、内容証明郵便を送って時効を延ばせるのは1回のみです。
翌月にも内容証明郵便を送ったからといって時効の延長が更新されるわけではないので、その点は念頭に置いておきましょう。
時効が迫っているときにも、支払督促は有効です。
支払督促は売掛先の財産の差し押さえができるほどの強い力があるため、売掛金を回収することができます。
ただし、売掛先から異議が出た場合は訴訟に移行します。
訴訟になると売掛先側の住所の裁判所まで出向く必要があるため、遠方だと手間がかかります。
売掛先の会社と近い場合に、支払督促を行うと良いかもしれません。
時効を更新・完成猶予したい場合は、民事調停の申し立てを行うと良いでしょう。
民事調停は売掛金の回収に向けて話し合うため、円満な解決ができるという特徴があります。
また、ポイントを絞って話し合いが行われるので、解決までの時間が短いことも魅力です。
民事訴訟では、裁判所を通じて判決を下してもらうことができます。
そのため、売掛先が売掛金の入金に応じない場合は、有効な手段といえるでしょう。
ただし、民事訴訟を起こす場合は弁護士に依頼して売掛先の財産を調査しておく必要があります。
差し押さえできる財産がないと、勝訴しても債権の回収は難しくなります。
この他、民事訴訟は判決が下されるまでに時間がかかることもあります。
6か月を超えるケースもあるため、長期間かかることを念頭に置いておきましょう。
売掛先から売掛金が入金されない場合、請求書の未送付が原因の可能性もあります。
以下では、請求書を再度送っても時効が延長されるのかどうか、未送付だった場合の対処法についてご紹介します。
請求書が未送付のまま5年間放置された場合、後から請求書を送っても時効が完成しています。
そのため、時効の完成猶予はできません。
時効の完成を遅らせたい場合は、時効がくる前に内容証明郵便で催告するか、協議を行う旨の書面での合意を行う必要があります。
請求書の未送付が発覚したら、すぐに上司に報告するようにしましょう。
請求書が送られていない場合、売掛金の入金がされず会社の資金繰りに影響します。
くわえて、「管理ができていない」と売掛先からの信用も失ってしまう可能性があるでしょう。
そうなると、今後の取引にも影響を及ぼす恐れがあります。
上司に報告した後は、個人の判断で対応せずに指示を仰ぎましょう。
売掛先に連絡をして理解を得られたら、すぐに請求書の再発行を行いましょう。
請求書の入金日は、売掛先と話し合って決めておく必要があります。
もし以前作成したものの、売掛先に送付していない場合はその請求書を編集して再発行するのも良いですが、入金日の記載には注意しなければなりません。
記載に漏れやミスがないか、売掛先が希望する入金日になっているかを確認してから請求書を送付しましょう。
請求書の未発送が発生したら、原因を特定することが大切です。
「次回から気をつけよう」だけで済ませてしまうと、具体的に何に気をつければ良いのかがわかりません。
また同じミスを繰り返してしまうため、原因を追求する必要があります。
原因を特定したら、再発防止策を講じましょう。
対策としては、請求書の送付を忘れてしまわないように売掛先ごとに売上管理を行ったり、請求書にナンバリングを行ったりすることが挙げられます。
また、1人で管理をすると確認漏れにより再度同じミスを起こしてしまう可能性があるため、複数人で管理すると良いでしょう。

貸倒損失とは、売掛金の回収ができなくなったときに損失額を処理する勘定科目のことです。
貸倒損失として計上することにより、法人税を減税することができます。
ただし、貸倒損失が認められているのは以下の3つのケースだけです。
・法律上の貸倒れ
・事実上の貸倒れ
・形式上の貸倒れ
それぞれ以下にて解説します。
法律上の貸倒れは、会社法や民事再生法などの適用により売掛債権が法的に消滅した場合に貸倒損失として計上することができます。
法律上の貸倒れに区分されるものは以下のとおりです。
| 1 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額 2 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額 3 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額 引用:No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 |
法律上の貸倒れは、その事実が発生した事業年度の損金の額に算入されます。
なお、損金経理を忘れていたとしても法律上債権が消滅しているので、自動的に損金算入されます。
事実上の貸倒れは、売掛債権が法的に消滅してはいないものの、売掛先の状況から入金してもらうことが明らかに無理だと判断された場合に貸倒損失として計上することができます。
ただし、事実上の貸倒れとして計上できるのは「債権の全額が回収できない場合」です。
そのため、担保物がある場合はその担保物を先に処分しなければなりません。保証人がいる場合は、その保証人から回収を行う必要があります。
これらをすべて済ませた後に、事実上の貸倒れとして損金算入することができます。
形式上の貸倒れは、以下のような事実が発生した場合に、備忘価額(※)を控除した残額を貸倒れとして損金算入をすることができます。
| 1 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき (ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。) なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。 2 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合 引用:No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 |
なお、債権を全額回収できない場合でも、形式上の貸倒れとして損金算入が可能です。
※税務上や会計上では、その資産が残っていることを忘れないようにするために付ける金額のこと

時効完成までに5年あるとはいえ、あっという間に時間は過ぎますし、そのまま請求を忘れてしまう可能性もあります。
また、時効が完成するまでに時間がないと、間に合わなくなってしまうこともあるかもしれません。
売掛金が未回収になる前に、弁護士に相談したりファクタリングを依頼したりしましょう。
弁護士に相談することで、交渉をスムーズに進めることが可能です。
売掛先と長年の付き合いがある場合、今後の関係も考慮すると催促しにくいことがあるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼をすれば代わりに交渉をしてくれるため「信頼関係が崩れてしまわないか」と、過度に心配する必要はないのです。
この他、売掛先が売掛金の支払いを頑なに拒否する場合は、訴訟や強制執行などの法的措置を取ることができます。
早めに弁護士に依頼をしていれば、訴訟などの手続きがスムーズに進むでしょう。
売掛金が未回収となる前に、早めにファクタリングを利用するのもおすすめです。
ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社が買取るサービスです。
売掛先からの入金日よりも早く現金化できるため、資金繰りの改善に役立てることができます。
また、売掛金の未回収リスクも低減できるでしょう。
ただし、支払期日を過ぎた売掛金はファクタリングの対象外になるため、その点は注意してください。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】
売掛金の時効は、2020年民法改正施行により「5年」と定められています。
5年を過ぎると時効が完成してしまうため、それまでに売掛金を入金してもらわなければなりません。
時効までに余裕がある場合は、「売掛先企業の担当者へ連絡する」「内容証明郵便を送る」「支払督促の申請を行う」などの手段を取るようにしましょう。
時効が迫っている場合は、「更新または完成猶予を行う」「権利についての協議を行う旨の書面による合意を得る」「売掛金の一部の弁済を開始してもらう」「売掛金債務の承認をしてもらう」「内容証明郵便による催告を行う」「支払督促を行う」「民事調停の申し立てを行う」「民事訴訟を起こす」などの方法が有効です。
売掛先からの売掛金の入金が遅れるようであれば、ファクタリングを利用するのも一案です。
一般社団法人日本中小機構金融サポート機構では、ファクタリングサービスをはじめ、お客さまに適した資金調達の方法をサポートしています。
資金繰りでお悩みの方は、ぜひ当機構にご相談ください。