

Same day
Procurement
Diagnostics
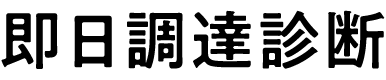
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

売掛金を早急に資金化できるサービスであるファクタリングは、利用者(債権者)側にさまざまなメリットをもたらします。
一方、売掛金の債務者である売掛先にとって、ファクタリングはどのような扱いとなるでしょうか。
今回は、ファクタリングにおける債権者と債務者のメリットを整理し、債務者側が申し込む「リバースファクタリング」についても解説します。
【注目】ファクタリングの利用を検討中の方へ
ファクタリングは、売掛金を売却することで資金を調達できるサービスです。
支払期日より前に資金を確保できる、売掛金の未回収リスクを軽減できるなど、さまざまなメリットがあります。
当機構は、関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」なので、どのファクタリング会社を選べばいいか迷っている場合も安心してご相談いただけます。
また、審査完了まで最短10分、振込まで最短40分で完了する、AIファクタリング「FACTOR⁺U(ファクトル)」も提供しています。
資金調達についてお悩みの場合も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
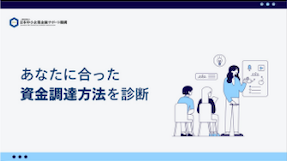
本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。
ファクタリングにおいて、債権者は「お金を受け取る権利を持つ人、または企業」のことを指します。
具体的には、売掛先に対して売掛金を請求できる立場にある企業や個人が該当します。
債権者は、商品やサービスを提供した後、その対価として一定の期日までに代金を受け取る権利、すなわち売掛金を持っています。
ただし、自社の資金繰りを早急に改善したいと考える場合、本来の支払期日より前に売掛金を現金化出来るファクタリングを利用します。
例えば、自社が取引相手の企業に300万円の商品を納品した場合、掛取引において代金はまだ支払われないため、自社は将来300万円を受け取る権利=売掛金を得ます。
この場合、自社が債権者に当たります。
一方、債務者は「お金を支払う義務を持つ人、または企業」を指します。
債務者は、売掛金の支払いを約束した売掛先が該当します。
先ほどの例では、商品の納品を受けた相手企業が債務者となり、300万円を期日までに支払う義務を負います。
ファクタリングのプロセスの中では、債権者と債務者の立ち位置はどう整理されるでしょうか。
例えば、ファクタリングの利用者である債権者が、300万円の売掛金をファクタリング会社に売却するとします。
このとき、利用者(債権者)はファクタリング会社から、売掛金の一部を手数料として差し引いた金額、例えば270万円を受け取るとします。
この段階で、売掛金の所有権は利用者からファクタリング会社に移り、ファクタリング会社が債権者となります。
そして、支払期日になったとき、債務者である売掛先は、売掛金である300万円をファクタリング会社に支払うことになります。
ファクタリングには債権者・債務者・ファクタリング会社の3者が関与しますが、売掛金を売却するにあたり債務者に承諾を得る必要がある場合(3者間ファクタリング)と、債務者に承諾を得ない場合(2者間ファクタリング)で手続きの形態が異なります。
3者間ファクタリングでは、債務者が直接ファクタリング会社に支払いを行います。
一方、2者間ファクタリングでは、債務者から承諾を得ない状態で売掛金の売却が行われるため、債務者から売掛金が入金された後、債権者(利用者)がファクタリング会社に支払いを行う必要があります。

ファクタリングは債権者側が申し込みを行って利用しますが、債権者と債務者の双方にとってメリットがあります。
債権者(利用者)にとって最大のメリットは、資金繰りを迅速に改善できる点です。
通常、売掛金の回収には一定の時間がかかりますが、ファクタリングを利用すれば、支払期日を待たずに資金を入手できます。
これにより、事業運営に必要な資金がスムーズに確保でき、急な出費や投資にも柔軟に対応できます。
もう一つの重要な利点は、未回収リスクを軽減できる点です。
ファクタリングは原則として「ノンリコース型」の契約となりますが、これは仮に売掛先が代金を支払えなくてもそのリスクが利用者に戻ってくることがない契約です。
ノンリコース契約により、利用者は売掛金を早期に資金化するだけでなく、未回収リスクからも解放されます。
一方、債務者(売掛先)にとってもファクタリングはメリットをもたらします。
まず、債務者側の支払条件やスケジュールが変更されることは通常ないため、既存のキャッシュフローに影響を与えません。
これにより、債権者(利用者)の資金調達ニーズを満たしながらも、自社の運営には支障が出ないという利点があります。
債権者(利用者)の資金繰りがファクタリングによって改善・安定すれば今後も継続的に取引を行うことが出来るので、ファクタリングの利用は債務者にとってもメリットがあると言えるでしょう。

債務者(売掛金の支払義務を負う側)が申し込んで利用する、「リバースファクタリング」というサービスもあります。
リバースファクタリングとは、通常のファクタリングとは異なり、債務者が主導して契約を行う資金調達方法です。
通常のファクタリングでは、売掛金を保有する債権者が資金調達を目的として申し込むのに対し、リバースファクタリングでは、債務者が申し込みを行ってファクタリングが実行されます。
リバースファクタリングでは、債務者がファクタリング会社と契約し、支払期日までの売掛金をファクタリング会社が買い取ります。
債権者はファクタリング会社から早期に支払いを受け取ることができ、債務者は通常の期日どおりにファクタリング会社に支払いを行います。
またリバースファクタリングを利用することで、申込者である債務者は買掛金(売掛金を債務者側から見たときの用語)の支払いを遅らせることが可能です。
例えば、掛金の本来の支払期日が60日後だった場合、リバースファクタリングを利用することで債権者側は支払期日が大幅に短縮され、債務者側は支払期日を120日後などに延ばすことができます。
また、下請法の要件を満たす目的でもリバースファクタリングが用いられます。
本来の支払サイト(売掛金の支払いまでの期間)が120日で、債務者が下請法の適用となる大企業だった場合、60日以内に支払わなければならないという決まりに反してしまいます。
リバースファクタリングを用いることで、下請先の債権者には60日以内に支払い、債務者はファクタリング会社へ120日以内に支払うということが可能になります。
リバースファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
発注企業が依頼する“リバースファクタリング”の仕組み・メリット・注意点
リバースファクタリングの手数料は、ファクタリングの仕組み上、売掛金の中から差し引かなければならない特徴があります。
そのため、最終的には債権者の受け取る金額が減少してしまいます。
通常のファクタリングと金銭の流れは同じで、申し込みの主体だけが債務者になったものがリバースファクタリングであると理解できます。
そのため、リバースファクタリングを導入する際には、手数料について債権者と事前に十分な合意を得る必要があります。
債務者がリバースファクタリングを利用することで、以下のようなメリットがあります。
リバースファクタリングを利用することで、債権者は売掛金を早期に資金化でき、資金繰りが大幅に改善されます。
これにより、外注先の財務状況が安定し、債務者も安心して取引を継続することができます。
債務者がリバースファクタリングを導入することで、債権者側の請求管理業務や回収業務の負担が軽減されます。
債務者も、支払プロセスが整理されることで、事務処理の効率化が図れます。
外注先の資金繰りをサポートすることで、取引関係が強化されます。
これにより、債務者は信頼できる外注先との関係を維持しやすくなり、優秀な外注先を囲い込むことが可能となります。
リバースファクタリングを利用する際は、以下のようなデメリットも押さえておく必要があります。
債権者にとっては、売掛金の一部が手数料として差し引かれるため、支払いが早い代わりに最終的な受取額が減少します。
債権者にとっては、早期資金化のメリットと手数料の負担を天秤にかける必要があります。
リバースファクタリングを提供しているファクタリング会社は、通常のファクタリングに比べてまだ少ない状況です。
これは、債務者主導の契約であるため、審査や契約条件が複雑になる点が背景にあります。
そのため、導入を検討する際には対応可能な会社を慎重に選定する必要があります。
リバースファクタリングでは、でんさい(電子記録債権)の利用が必須となります。
でんさいの導入には審査が必要なほか、そのためのインフラを整備する必要もあるかもしれません。
初期費用や手間がかかるため、特に中小企業にとっては負担となる場合もあります。
でんさい(電子記録債権)については下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングと電子記録債権(でんさい)の違いを解説!選ぶ際の基準もご紹介
ファクタリングは利用者(債権者)にとってメリットの多いサービスですが、売掛先(債務者)にとってデメリットがあるわけではなく、ケースによっては売掛先にもメリットをもたらします。
債務者側から申し込みを行うリバースファクタリングにおいては、双方にメリットがあるものの、債務者は債権者にメリットをしっかり伝え合意を得る必要があります。
日本中小企業金融サポート機構では、債権者から申し込みを行い、売掛金を早期資金化できるファクタリングサービスを提供しています。
2者間ファクタリング・3者間ファクタリングの双方に対応しているため、希望する条件に合わせて契約内容を選択できます。
また、買取可能金額の下限・上限を設けていない点も当機構の大きな特徴です。
AIを活用することにより、手続きがすべてオンラインで完結する「FACTOR⁺U(ファクトル)」もご利用いただけます。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。