

Same day
Procurement
Diagnostics
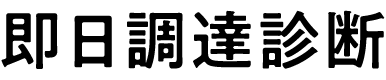
ファクタリングの調達可能額を
今すぐ確認いただけます
- 当機構では給料債権の買い取りは
行なっておりませんのでご了承ください
カテゴリ

農業では、種まきや苗の購入、肥料や農薬の手配、機械の燃料費など、収穫や販売による収入を得るまでに多くの支出が先行します。
そのため、これらの支出に対応するために、運転資金の確保が不可欠です。
そこで今回は、農業における運転資金の重要性や、農業の運転資金確保に使える5つの調達手段をご紹介します。
また、農業で融資の審査に通るポイントや資金調達の失敗パターンと対策についてもまとめているので、ぜひご参考にしてください。
【注目】資金繰りでお悩みの事業主様へ
早期に資金調達できる手段をお探しの場合は、売掛金を売却することでスピーディーに現金化できるファクタリングがおすすめです。
ファクタリングでは最短即日での資金調達も可能であり、急な支払いや資金繰りの改善に役立ちます。
当機構のファクタリングサービスは、手数料が業界最低水準となっており、1.5%~の手数料で売掛金の現金化が可能です。
また、関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する「経営革新等支援機関」でもあるため、安心して資金繰りについてご相談いただけます。
資金繰りでお悩みの事業主様は、この機会にぜひお問い合わせください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

農業を営む際は、運転資金の確保が欠かせません。
ここでは、農業において運転資金がなぜ重要なのか、資金不足が農業に及ぼす影響、さらに融資を受ける際の基準について解説します。
農業では、種子や苗の購入、肥料・農薬の調達、機械の燃料費、人件費など、収穫前から多くの支出が発生します。
しかし、実際に収入が得られるのは収穫・出荷後であり、現金が手元に入るまでに時間がかかります。
このように、農業では収入と支出のタイミングに時間差があるため、日々の経営を支えるためには運転資金が欠かせないのです。
資金繰りについては下記コラムで詳しく解説しています。
強い経営には必須?資金繰りの考え方・具体的な取り組み内容
運転資金が不足すると、必要な時期に資材を購入できなかったり、作業スタッフの確保が困難になったりと、農作業の進行に大きな支障をきたします。
その結果、播種や施肥、収穫などのタイミングを逃してしまい、収穫量や品質の低下を招く恐れがあります。
また、運転資金が不足し、既存の借入金の返済が滞ると、信用低下や追加融資の難航にもつながるでしょう。
こうした悪循環が続くと経営全体の安定が保てなくなり、最悪の場合、事業の継続が困難になることもあります。
農業において運転資金を確保する手段の一つが融資の活用です。
金融機関では融資の審査にあたって、過去の経営成績や返済能力、事業計画の内容をとくに重視します。
加えて、補助金や農業共済の利用状況も利用者の信用力に影響を与えることがあります。
融資を受けるためには、事前に収支計画を立て、必要な情報や書類を整理しておくことが重要です。

ここでは、農業における運転資金の調達手段を5つご紹介します。
JAバンクでは、農業者の経営支援を目的とした各種融資制度を提供しています。
その一つである「農業近代化資金」は、施設の取得・拡張や、設備・機具の購入、長期運転資金の確保などに活用できる農業経営の改善や拡大を支援するための長期・低利の制度資金です。
また、短期的な運転資金のニーズには、「農業経営改善促進資金(スーパーS資金)」「アグリマイティー資金」などが適しています。
なお、金利や返済条件は、融資の種類や利用者の経営状態・信用力などによって異なります。
日本政策金融公庫は、農業者や中小企業、小規模事業者などの資金調達を支援する公的な金融機関です。
「スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)」をはじめとした運転資金にも利用できる様々な融資制度を提供しており、審査に通過し融資を受けることができれば、資材費や人件費など、日常的な経営に必要な資金を確保することができます。
無担保・無保証で利用できる場合や、金利優遇措置がある制度もあり、若手農業者や新規就農者も利用しやすくなっています。
農業の運転資金を確保する手段の一つに、民間の金融機関を活用する方法があります。
都市銀行や地方銀行、信用金庫などでは、農業者向けの融資商品を取り扱っており、資材費や人件費、日常的な経営の資金調達として利用可能です。
融資の審査では、経営実績や返済計画の妥当性、担保・保証の有無などが重視されるので、書類の準備や返済計画の作成など事前の準備は怠らないようにしましょう。
地域に根ざした金融機関は地元の農業事情に理解があるため相談しやすく、条件交渉も行いやすいことがあります。
農業の運転資金を確保する方法の一つに、リースやローンの活用があります。
リースは、設備を購入せず一定期間使用し、契約期間終了後に返却する仕組みであり、一度に多額の資金を支出することなく、必要な機械や施設を使えるため、初期費用を抑えることができます。
一方ローンは、設備を購入するために金融機関などから資金を借り入れ、一定期間内に返済していく方法です。
どちらの方法も設備投資に伴う資金繰りの負担を軽減でき、経営の効率化を図ることが可能です。
農業の運転資金を確保する方法の一つに、ファクタリングの活用があります。
ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する資金調達手段です。
例えば、農産物を卸業者に出荷した後、入金までに時間がかかる場合でも、ファクタリングを利用することで必要な現金をすぐに確保できます。
また、ファクタリングの審査は融資と比較し比較的柔軟と言われており、自社の信用力に不安がある方や、融資の審査に通過できなかった方の資金繰りの改善策として注目されています。
ファクタリングには、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類の契約方法があります。
2者間ファクタリングは利用者とファクタリング会社で契約を締結するため、サービスの利用にあたり売掛先からの承諾が不要でスピーディーに資金を調達できるのが特徴です。
一方3者間ファクタリングでは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者間で契約を締結します。
2者間ファクタリングと異なり、サービスを利用する際に売掛先からの承諾が必要となりますが、3者間ファクタリングではファクタリング会社が売掛先に直接売掛金の存在を確認できるため、売掛金の未回収リスクを低く抑えられます。
これにより、3者間ファクタリングは2者間ファクタリングに比べて手数料が低く設定される傾向にあるのが特徴です。
ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。
ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】

JAバンクでは農業者の経営を支援するため、さまざまな融資制度を提供しています。
運転資金や設備投資、新規就農など目的に応じて使える融資があり、金利や返済条件も比較的利用しやすい内容となっています。
ここでは、JAバンクで利用できる代表的な4つの農業融資についてご紹介します。
JAバンクで利用できる「農業近代化資金」は、農業経営の合理化や近代化を図るための長期資金として活用されている公的融資制度です。
農業近代化資金は、農業機械の導入や施設の整備、農地の改良のほか、運転資金としての利用も可能です。
金利は比較的低利で、条件を満たせば利子補給を受けられる場合もあります。
利子補給とは、農業者などが借りた融資に対して発生する利息の一部または全部を、国や自治体が補助する制度のことです。
これにより、農業者の金利負担が軽減され、必要な設備投資や運転資金の確保がしやすくなります。
農業近代化資金は、一般的に担い手農業者や新規就農者によって活用されており、安定した農業経営を目指す上で有効な選択肢の一つといえます。
「農業経営改善促進資金(スーパーS資金)」は、認定農業者が農業経営改善計画の達成に必要な短期運転資金を融資する制度です。
主な資金使途としては、以下が挙げられます。
| ・種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃などの直接的現金経費 ・小農具等営農用備品、消耗品等の購入費 ・営農用施設・機械の修繕費 ・地代(賃借料)、営農用施設・機械のリース・レンタル料 ・生産技術、経営管理技術の習得費 ・市場開拓費、販売促進費 |
農業経営改善促進資金は、経営改善計画に基づいた投資を支援するため資金使途が明確となっています。
また、特定の条件を満たす場合には、利子補給や金利優遇が受けられることもあります。
これにより、農業者は安定した経営を実現できるようになります。
「アグリマイティー資金」は、農業者の多様な経営ニーズに柔軟に対応するために設けられた融資制度です。
運転資金から設備資金まで幅広く対応しており、農業者の実情に合わせて融資内容を調整することが可能です。
例えば、播種や収穫前の資材購入に必要な短期の運転資金には、1年以内の返済期間を設定した融資が利用でき、ビニールハウスの新設やトラクターの導入といった設備投資には、数年から10年程度の期間を設定した融資が利用できます。
アグリマイティー資金は、担保や保証の有無、金利などの条件が利用者ごとに異なります。
そのため、具体的な内容については、最寄りのJAバンク窓口で確認することをおすすめします。
「JA農機ハウスローン」は、農業者が農業用機械やビニールハウスなどの施設を導入・整備するための資金をサポートしてくれる融資制度です。
トラクターやコンバインなどの大型機械から、小規模な設備の整備まで幅広く対応しており、自身の貯蓄だけでは購入や導入が難しい場合の設備投資をサポートしてくれます。
設備の導入によって作業効率の向上が期待でき、経営の安定にもつながります。

日本政策金融公庫では、農業者の多様なニーズに応じた融資制度が整備されており、新規就農者から長年活動している農業者まで、幅広い層に活用されています。
ここでは、日本政策金融公庫で利用できる代表的な5つの農業融資についてご紹介します。
「スーパーL資金」は、認定農業者が農業経営改善計画に基づき、農業経営の基盤を強化するために利用できる長期融資制度です。
土地の取得や施設・機械の導入、果樹の植え付けなど幅広い用途に対応しており、運転資金としても利用することができます。
また、条件を満たせば利子補給制度が適用されることもあり、金利負担の軽減を図れます。
認定農業者として計画的な経営を進めたい方にとって、強力な資金支援の手段となるでしょう。
「経営体育成強化資金」は、担い手農業者や集落営農組織などが農業経営の発展や体制強化を図るために利用できる融資制度です。
農業用施設の整備や機械の導入、土地の取得など、成長段階に応じた幅広い用途に対応しています。
新規就農者や、規模拡大を目指す農業者にも活用されており、条件を満たすことで金利優遇措置や利子補給が受けられる場合もあります。
日本政策金融公庫が提供している「農業改良資金」は、農業経営の改善や技術向上を目的とした無利子の融資制度です。
そのため、農業改良資金を活用することで返済負担を抑えながら中長期的な経営強化や競争力の向上に向けた投資を行うことができます。
農業改良資金の融資対象となるのは、農林漁業バイオ燃料法や米穀新用途利用促進法に基づく認定を受けた農業者・生産者などです。
農業経営改善計画や技術導入計画に沿って、機械の導入、施設整備、新技術の試験導入など、さまざまな取り組みに現金を充てることができます。
「青年等就農資金」は、新たに農業を始める青年や就農希望者を支援するための無利子融資制度です。
認定新規就農者が対象で、農業経営の開始に必要な設備資金や運転資金など、幅広い用途に対応しています。
返済期間は17年以内(据置期間5年以内)と長期にわたり設定されているため、青年等就農資金を活用することで、就農初期の負担が軽減でき、安定した経営基盤を築くための時間的な余裕が生まれます。
このような特徴から、青年等就農資金は新規就農に挑戦する若手農業者にとって非常に有効な資金調達手段といえます。
日本政策金融公庫が提供している「農林漁業セーフティネット資金」は、農業者や漁業者が自然災害や価格暴落などの突発的なリスクに直面した際に、経営の安定を図るための融資制度です。
農林漁業セーフティネット資金は農業経営や漁業経営の維持・再建を目的としており、主に以下のような用途に活用されます。
| ・自然災害や病害虫による被害からの復旧費用 ・農産物価格の急落による収入減少に対応するための資金 ・経営の再建や改善に必要な投資資金 |
農林漁業セーフティネット資金の融資条件や金利、返済期間などは、個別の状況や被害の程度に応じて柔軟に設定されます。

JAバンクや日本政策金融公庫などの制度融資では、一定の要件や審査基準が設けられており、事前の準備が審査通過のカギを握ります。
ここでは、農業で融資の審査に通るためのポイントを解説します。
融資の審査を有利に進めるためには、「認定新規就農者」の認定を市町村から受けることが重要です。
認定新規就農者とは、就農後おおむね5年以内で、作成した「青年等就農計画」が市町村に認められた人のことを指します。
認定新規就農者の認定を受けることで、「青年等就農資金」などの無利子融資制度を利用できるほか、各種支援制度や優遇措置の対象になる可能性が高まります。
就農後5年以上経過しており、認定新規就農者として認定されていない場合は「認定農業者」として自治体から認定を受けるのがおすすめです。
認定農業者とは、自ら作成した「農業経営改善計画」が市町村に認められた農業者のことを指し、認定を受けることで計画的な経営に取り組んでいる証とされます。
融資制度の中には認定農業者を対象とした優遇措置が設けられており、金利の引き下げや借入限度額の拡大などのメリットを受けられる場合があります。
計画的かつ継続的に農業を行う意志を示すことで、金融機関からの信頼性も高まります。
農業で融資の審査に通るためには、説得力のある事業計画書の作成が欠かせません。
収支予測や資金の使途、将来の経営ビジョンなどを具体的に示すことで、金融機関に「返済可能な計画である」と判断されやすくなります。
また、どのような作物を栽培し、どの市場で販売するのか、収益化までのスケジュールなどを明確に記載することも重要です。
過去の経験や取得予定の資格など、自身の強みも積極的に盛り込むと良いでしょう。

農業における資金調達は、経営の安定や成長に直結する重要なステップですが、準備不足や誤った判断により資金の調達に失敗してしまうケースも少なくありません。
ここでは、資金調達の失敗パターンと、その対策についてご紹介します。
農業で資金調達を行う際に多い失敗の一つが、事業計画や収支計画の作り込みが不十分なことです。
融資を受けるためには、明確な経営ビジョンと数字に基づいた根拠が求められます。
例えば、収益の見通しが甘い、費用の内訳が曖昧といった状態では、金融機関からの信頼を得るのは難しくなります。
対策としては、作物の市場価格や生産コストなどの具体的なデータを活用し、現実的かつ説得力のある計画書を作成することが挙げられます。
農業における資金調達でありがちな失敗の一つが、資金の使途が曖昧なことです。
何にどれだけの資金が必要なのかが明確でないと、融資審査で不利になるだけでなく、仮に融資を受けられたとしても調達後の資金管理が不透明になりがちです。
例えば「設備投資のため」だけではなく、「温室設置に300万円」「育苗器具に50万円」など、具体的な内訳を提示することで、金融機関からの信頼性が高まり審査に通る可能性があります。
農業は天候や自然災害の影響を大きく受けるため、資金調達においてもこれらのリスクを見越した計画が求められます。
にもかかわらず、収穫量や売上を楽観的に見積り、災害時の対応策や予備資金の確保を怠るケースも少なくありません。
こうしたリスクを想定していないと、いざというときに返済不能に陥る可能性があります。
対策としては、収入保険への加入や、農林漁業セーフティネット資金などの支援制度を事前に把握し、リスクに備えた柔軟な資金計画を立てることが挙げられます。

農業を安定的に続けていく上で、資材や人件費などにかかる運転資金の確保は欠かせません。
こうした資金負担を軽減する手段の一つが、補助金や助成金の活用です。
ここでは、補助金・助成金を利用するメリットや、融資との併用による資金戦略、農業者におすすめの補助金・助成金・交付金についてご紹介します。
補助金・助成金のメリットの一つは、原則返済の必要がないことです。
そのため、資金調達による将来的な負担を抑えながら、調達した資金を必要な設備投資や運転資金に充てることができます。
とくに新規就農者や規模拡大を目指す農業者にとっては、経営初期の資金調達の大きな助けとなるでしょう。
さらに、補助金や助成金は、特定の目的に対して交付されるものが多いため、省エネ設備の導入やICT技術の活用、若手農業者の支援など、自身の経営方針と合致した制度を選べば、より効果的な資金活用が可能です。
また、制度によっては専門家による事業計画の作成サポートを受けられるケースもあり、経営の見直しや改善にもつながります。
このように、補助金・助成金は単なる資金の補填にとどまらず、農業経営の質を高めるためのきっかけにもなり得る制度です。
補助金・助成金については下記コラムで詳しく解説しています。
助成金と補助金の違いをわかりやすく解説!管轄・予算・給付額・期間の相違点とは
補助金や助成金は返済不要の資金調達方法として農業経営を支える強力な手段ですが、申請から交付までに時間がかかる場合があります。
そこで、融資と組み合わせることで資金繰りの安定性を高める戦略が有効です。
例えば、すぐに必要な運転資金は融資で確保し、設備投資や長期的な取り組みには補助金を充てるなど、目的に応じた使い分けが重要です。
補助金と融資を組み合わせることで、資金面のリスクを分散し、より安定した農業経営を実現できます。
ここでは、農業におすすめの補助金・助成金・交付金をご紹介します。
「農業次世代人材投資資金」は、新たに農業を始める若者を支援するための制度で、就農前後の段階に応じて現金が支給されます。
就農準備資金(準備型)は、農業研修を受ける期間の生活費などを支援し、経営開始資金(経営開始型)は、就農初期の所得を補い、農業経営の確立を後押しすることを目的としています。
いずれも原則として返済不要で、一定の条件を満たすことで受給可能です。
「移住支援金」は、都市部から地方へ移住し、地方での就業や起業を目指す人を対象とした制度です。
都道府県と市町村が連携して実施しており、要件を満たせば最大で100万円(単身の場合は最大60万円)の支援を受けられます。
移住支援金は地域の担い手不足解消や農業の活性化を目的としており、移住先での就農支援や研修制度と組み合わせて活用することで、よりスムーズに農業を始める環境を整えることができます。
「起業支援金」は、地方で新たに起業を目指す人を対象とした補助制度で、農業分野での起業にも活用できます。
地域課題の解決につながる事業として認められれば、最大200万円の支援を受けられるケースもあります。
起業支援金は移住支援金と併用できる場合もあり、農業を含む地域でのビジネス立ち上げにかかる初期費用の負担を大きく軽減できる点が魅力です。
なお、市町村が主体となって実施しているため、申請には自治体ごとの要件確認が必要です。
「雇用調整助成金」は、経済的な理由により一時的に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために活用できる制度です。
農業分野でも、天候不順や市場変動、災害などで作業量が減少し、従業員の休業を余儀なくされる場合などに活用が可能です。
休業手当の一部が助成されるため、経営者は人件費の負担を軽減しながら雇用を守ることができます。
「環境保全型農業直接支払交付金」は、環境に配慮した農業活動を推進するために、農業者に対して支給される交付金です。
対象となる活動には、農薬や化学肥料の使用削減、土壌や水質の保全、生物多様性の維持などが含まれます。
農業者は、環境保全に取り組むことによって環境負荷の軽減を図りながら、環境保全型農業直接支払交付金を受け取ることができます。
なお、環境保全型農業直接支払交付金の受給額は、農業者が取り組む活動内容や面積に応じて決定され、農地の規模や地域によって異なります。

農業の資金繰りには、ファクタリングの利用もおすすめです。
ここでは、ファクタリングを利用するメリットやデメリット・注意点をご紹介します。
ファクタリングを利用するメリットは以下の通りです。
農業では、出荷から入金までに時間がかかることが多く、その間の資金繰りが課題となります。
しかし、ファクタリングを活用することで、売掛先からの入金を待たずに必要な資金を確保できるため、仕入れや人件費、設備修繕費などの支払いにも柔軟に対応することができます。
審査も融資と比較しスピーディーで、2者間ファクタリングを利用すれば最短即日での現金化が可能な点も大きな魅力です。
ファクタリングを利用するメリットには、売掛金の未回収リスクを回避できる点も挙げられます。
ファクタリングの契約は、原則償還請求権なしのノンリコース契約となっています。
そのためファクタリングを利用すれば、売掛先が万が一倒産などの理由で支払いが行えない状況になっても償還請求権なしの契約により、利用者がファクタリング会社に費用を請求されることはありません。
ファクタリングを利用することで売掛金の未回収リスクを回避でき、安定した資金繰りを維持することができます。
ファクタリングを利用するメリットには、財務状況が悪くても利用できる可能性がある点も挙げられます。
一般的な融資と異なり、ファクタリングでは利用者の信用力ではなく、売掛先の信用力が重視されます。
そのため、赤字決算や税金の滞納がある場合でも、売掛先が信頼できる企業であればファクタリングを利用できる可能性があります。
資金繰りが厳しい局面でも、ファクタリングの利用は経営を立て直す手段として有効です。
ファクタリング利用時のデメリット・注意点は以下の通りです。
ファクタリングを利用する際のデメリットの一つに、手数料が発生する点があります。
ファクタリングでは売掛金の一部が手数料として差し引かれるため、実際に手元に入る金額は売掛金の額より少なくなります。
手数料の相場は、2者間ファクタリングで8%~18%、3者間ファクタリングで2%~9%とされており、利用するファクタリング会社や売掛金の内容によっても変わってきます。
頻繁に利用する場合や高額取引を行う場合は手数料の負担が大きくなる可能性があるため、事前に複数社を比較し、条件をよく確認することが大切です。
ファクタリングを利用する際のデメリットに、調達できる現金の上限が売掛金の額面までであることが挙げられます。
融資の場合は事業計画や担保・保証人の有無などを踏まえた審査により、必要な金額に応じた融資が受けられます。
しかし、ファクタリングは売掛金の売却となるため、保有している売掛金の額面以上の金額は調達することができません。
これにより、調達できる額が希望する資金額に届かない可能性があります。
ファクタリングを利用する場合、売掛先から資金繰りの悪化を懸念されるリスクがあります。
3者間ファクタリングでは、サービスの利用にあたり売掛先からの承諾が必要なため「資金繰りが悪化しているのでは?」と思われる可能性があります。
これにより、利用者の信頼性や売掛先との取引条件に影響を与える可能性があります。
3者間ファクタリングを利用する場合は、利用前に売掛先との関係を慎重に考慮し、影響を最小限に抑える方法を検討することが重要です。

ここでは、農業の運転資金調達におすすめのファクタリング会社・サービスをご紹介します。
「日本中小企業金融サポート機構」は、企業の資金調達における課題を解決するために、柔軟かつ多様なサービスを提供しているファクタリング会社です。
オンラインで完結する手続き体制を整えているため、全国どこからでもスムーズにファクタリングの利用が可能です。
日本中小企業金融サポート機構の公式HPでは、即日調達診断が利用できます。
簡単な質問に答えるだけで、10秒程度で調達可能な額を確認できるため、自分がファクタリングで調達できる額が気になる方は、即日調達診断を利用してみましょう。
さらに、日本中小企業金融サポート機構は最短3時間で入金が可能な点も強みで、17時までに契約が完了すれば最短即日現金化が実現できます。
これにより、急な資金ニーズにも迅速に対応することができます。
また、同機構は買取可能額に下限・上限を設定していません。
売掛金が数千万円に達する場合でも買取可能額に制限がないため、大規模な資金調達にも対応可能です。
経営の安定化を図りたい事業主様は、ぜひご利用ください。
「FACTOR⁺U」は、日本中小企業金融サポート機構が提供するAIファクタリングサービスで、迅速かつ手軽に資金調達ができる点が大きな特徴です。
ファクタリングを利用するにあたって、面談や対面での手続きは一切不要で、申し込みから審査完了までは最短10分、入金まで最短40分と非常にスピーディーなサービスとなっています。
また、FACTOR⁺Uでは、最低1万円からの買い取りに対応しているため、小規模な売掛金でも利用しやすく、個人事業主やフリーランスの方にとっても頼れる存在です。
もちろん、法人の利用にも対応しており、手数料は1.5%〜とリーズナブルで、売掛金の上限額に制限がないため、大口取引にも対応可能です。
全ての手続きがオンラインで完結し、忙しい事業主様でも時間を取られずに活用できるため、資金調達をご検討中の方はぜひFACTOR⁺Uを利用してみてはいかがでしょうか。
「ビートレーディング」は、豊富な実績と高い柔軟性を備えたファクタリング会社です。
幅広い業種や事業規模に対応しており、法人から個人事業主まで、資金調達のさまざまなニーズに応じた提案を行っています。
ビートレーディングでは、初めてファクタリングを利用する方も安心できるよう、専任の担当者が丁寧にヒアリングを行い、最適なプランを提案しています。
最短2時間で入金可能というスピーディーな対応だけでなく、顧客ごとの状況に合わせた柔軟な審査体制も好評を得ています。
「みんなのファクタリング」は、スピードと利便性を重視した中小企業・個人事業主・フリーランス向けのファクタリングサービスです。
面談や電話対応が一切不要な完全非対面型で、スマホやPCから簡単に申し込みが可能です。
書類のアップロードもオンラインで完了するため、忙しい日常の中でもスムーズに資金調達が行えます。
みんなのファクタリングは利用者の利便性を最優先しており、審査の透明性やスピード感、そして土日祝日の対応体制が整っている点が大きな魅力です。
とくに急な資金ニーズに即対応できる体制は、多忙な事業主様にとって強い味方となるでしょう。
「Mentor Capital」は、柔軟な対応と高い審査通過率を誇るファクタリング会社として、多くの中小企業や個人事業主から支持を得ています。
取引形態は2者間ファクタリング・3者間ファクタリングに対応しており、さまざまな業種で利用することが可能です。
Mentor Capitalは契約後の入金スピードにも定評があり、必要書類が整っていれば即日現金化も期待できます。
さらに、担当者による丁寧なヒアリングとサポート体制も充実しており、初めてファクタリングを利用する方でも安心して手続きを進められます。
農業経営において安定した生産活動を維持し、経営の持続性を確保する上で運転資金は欠かせません。
季節性や自然環境の影響を受けやすい農業では、収入と支出のタイミングにズレが生じやすいため、計画的な資金管理が求められます。
農業で利用できる資金調達手段には、JAバンクによる融資、日本政策金融公庫の各種制度資金、民間の金融機関による融資に加え、農業機械や施設の導入に活用できるリース・ローン、さらに売掛金を活用したファクタリングなど、さまざまな手段があります。
農業者自身の経営状況や資金の用途に応じて、適切な手段を選択しましょう。
当機構は、関東財務局長および関東経済産業局長から「経営革新等支援機関」に認定されているファクタリング会社なので、安心してご利用いただけます。
また、オンライン完結型のファクタリングサービスを提供しており、全国どこからでも申し込みが可能です。
当機構のAIを活用したファクタリングサービス「FACTOR⁺U」では、迅速な審査を実現しています。
審査が完了するまで最短10分、現金の振り込みまで最短40分で対応可能です。
資金調達を急ぐ事業主様は、ぜひ当機構のサービスをご利用ください。
当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。